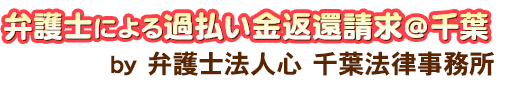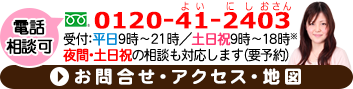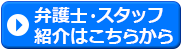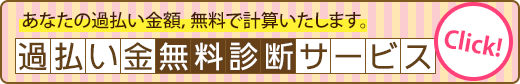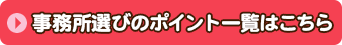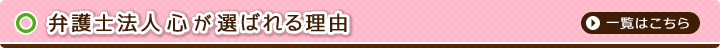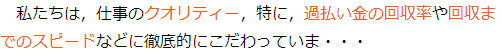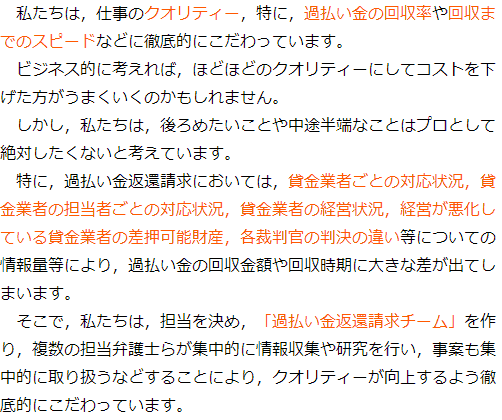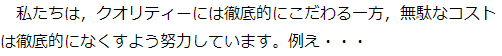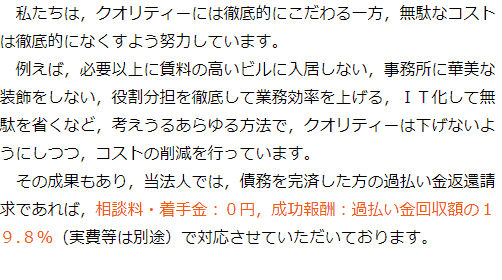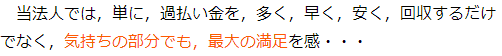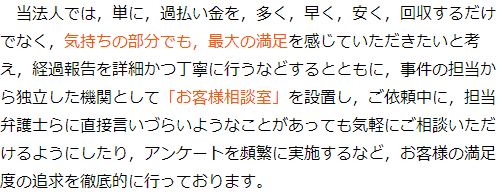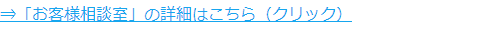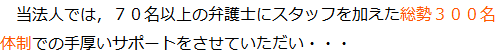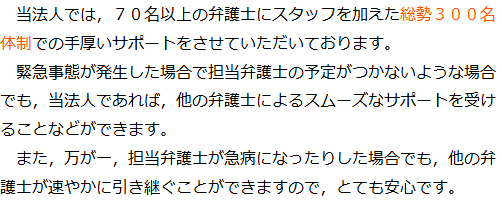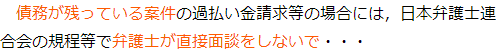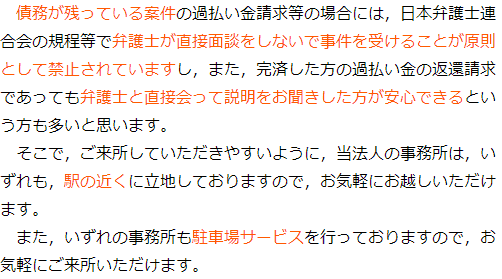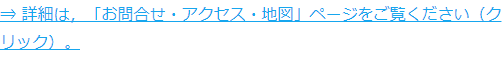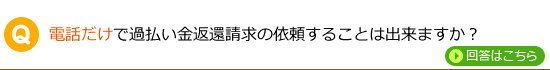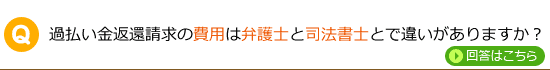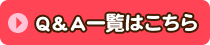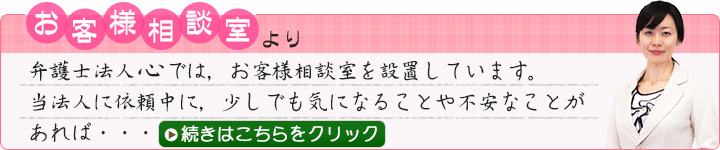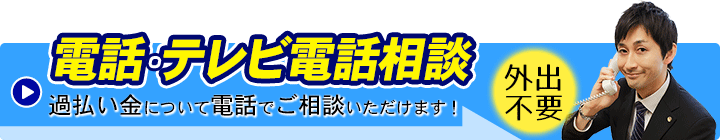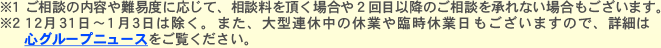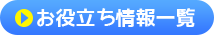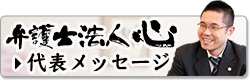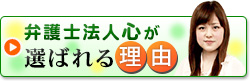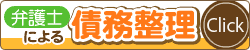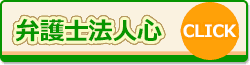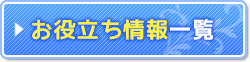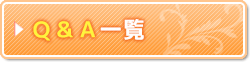千葉からも便利に相談可能
駅近くの立地に事務所があり,ご来所の際にもとても便利です。また,すでに完済されている方の過払い金返還請求はお電話での対応も可能です。
過払い金返還請求の流れ
1 弁護士への相談と依頼

過払い金返還請求は、まず弁護士への法律相談から始まります。
相談を受けた弁護士は、業者名や取引時期など必要な情報の聴き取りを行います。
その結果、過払い金が発生している可能性があると判断した場合は、依頼いただいた場合の費用をご説明し、委任契約を締結することとなります。
2 受任通知の送付と取引履歴の取り寄せ
過払い金返還請求の依頼を受けた弁護士は、対象業者に受任通知を送付し、取引履歴の開示を求めます。
この取引履歴には借り入れや返済の年月日や金額など、過払い金の計算に必要な情報が記載されています。
取引履歴が開示されるまでの期間は業者によって異なりますが、早ければ2週間程度、遅いと2か月程度かかることもあります。
3 過払い金の計算
取引履歴が開示されたら、過払い金の計算作業に入ります。
計算結果は1週間から2週間程度で判明します。
4 過払い金の請求
過払い金の金額が判明しましたら、書面をもってその金額の返還を業者に請求し、回答を求めることになります。
回答期限は2週間後程度を設定しますが、業者によっては、業務過多などの理由から期限内に回答がないケースもあります。
5 返還交渉
過払い金の返還請求に対する回答がありましたら、金額と返還日について交渉を開始します。
この交渉は1回の電話でまとまる場合もありますが、数回の交渉が必要になる場合もあります。
交渉がまとまりましたら、その内容(返還金額と返還日)について依頼者の方に検討いただき、問題ないということでしたら業者と和解することになります。
金額等に納得がいかない場合は再度交渉します。
再交渉でも納得のいく金額等にならない場合は、訴訟を検討することになります。
6 訴訟
大きな争点があり、訴訟前の交渉だと納得のいく金額での和解ができない場合は、訴訟を提起することになります。
また、大きな争点がない場合でも、訴訟前の交渉では、業者にもよりますが和解金額はやや低くなる傾向がありますので、十分な金額の返還を求める場合は、訴訟による解決を行うことになります。
訴訟を提起した場合でも、最終的に和解によって解決するケースもあります。
7 和解金の入金
和解金は法律事務所の預り金口座に振り込まれますので、和解により決めた日にちに和解金の入金がありましたら、弁護士報酬や実費の精算を行い、依頼者の方にお支払いして手続き終了となります。
以上が過払い金返還請求の大まかな流れとなります。
過払い金が発生する可能性がある人
1 過払い金が発生する理由

利息制限法は、10万円未満の貸し付けについては20%、10万円以上100万円未満の貸し付けについては18%、100万円以上の貸し付けについては15%という上限利率を定めています。
他方、出資法は、現在は20%を超える金利での貸し付けに刑事罰を科していますが、2010年6月に改正法が施行される直前は29.2%でした(なおこの出資法の上限金利は何度か改正され段階的に引き下げられていました)。
また、貸金業法は、当該法律が適用される貸金業者について、利息制限法の上限利率を超える利率の利息を受領した場合でも、一定の要件をみたす場合は有効になるという規定(みなし弁済といいます)を置いていましたが、同じく2010年6月に廃止されました。
過払い金は、貸金業者が利息制限法を超える利率で貸付を行っていたが、みなし弁済が適用されるための要件を充たしておらず、利息制限法を超える部分の利息の約定が無効になることにより発生します。
そのため、みなし弁済が廃止された2010年6月以降に初めて消費者金融やクレジットカード会社と契約し借り入れやキャッシングを始めた場合は、過払い金は発生しません。
2 貸金業法が適用されない業者
貸金業法は銀行や信用金庫、信用組合には適用されません。
そのため、銀行は利息制限法の制限利率を超える金利での貸し付けは行っていません。
そのため、例えば1995年からM銀行のカードローンを利用しているという場合でも、過払い金は発生していません。
3 貸金業法が適用されない取引
貸金業法は金銭の貸し付けに適用されます。
そのため、クレジットカードの場合、過払い金が発生する可能性があるのはローンまたはキャッシングになり、ショッピングでは発生しません。
また、車や家電等をショッピングクレジットで購入した場合も、過払い金は発生しません。
4 過払い金が発生する可能性がある人
以上をまとめると、過払い金が発生する可能性があるのは、2010年6月より前から、貸金業法が適用される消費者金融やクレジットカード会社から借り入れを行っていた方ということになります。
ただし、多くの消費者金融やクレジットカード会社は、2007年頃までには新規契約の貸付利率を利息制限法の上限金利以下に引き下げており、また、一部の業者(SMBCモビットなど)は利息制限法の上限利率を超える利率での貸し付けを一切行っていません。
さらに、業者から優良顧客と認定された場合は、早い時期から貸付金利が利息制限法の上限利率以下に下がっている場合もあります。
そのため、実際に過払い金が発生しているかどうかは、取引履歴の確認等によりケースバイケースで判断する必要があります。
過払い金の相談で必要となる資料
1 過払い金の相談と依頼後の手続きの流れ

2010年6月18日に施行された改正貸金業法により、利息制限法の上限利率を超える利率での貸し付けをすることはできなくなりました。
多くの業者は、2010年6月18日より前から新規契約者に対する貸付利率を利息制限法の上限利率以下に引き下げていましたが、過払い金が発生しているかどうかということについては、2010年6月17日以前から消費者金融会社またはクレジットカード会社と借り入れ(カードローン、キャッシング)の取引をしていたかどうかということが一つの目安になります。
過払い金の相談を受けた弁護士は、取引業者や借り入れ時期等の情報を基に過払い金発生の有無を判断し、発生している可能性がある場合は、依頼を受け手続きを進めることになります。
過払い金返還請求について依頼を受けた弁護士は、対象業者に対し受任通知を送付し、取引履歴という借入および返済の年月日および金額などが記載されている書類の開示を求めます。
そして、開示された取引履歴を基に過払い金の計算をして、対象業者にその返還を請求することになります。
2 過払い金の相談の際に必要となる資料
以上のように、過払い金の請求は、借り入れをしていた業者名を特定することができれば進めることが可能です。
そのため、過払い金の相談の際は、原則として資料がなくても問題はありません。
なお、借り入れの開始時期は、ATMの明細が残っていれば、そこに「基本契約日」が記載されている場合があるため、特定することが可能な場合もあります。
ですが、取引の継続中に契約の切り替えを行っている場合は、基本契約日は切り替え後の契約の契約日になりますので、当初の契約の契約日まではわかりません。
そのように当初の契約の時期があいまいな場合でも、弁護士にご相談ください。
3 業者名が特定できない場合
なお、ATM明細等が残っておらず、借り入れをしていた業者名が特定できない場合でも、以下の方法により業者名を調べることが可能です。
業者名を特定する手掛かりとなる資料がない場合でも、お気軽にご相談ください。
① JICCおよびCICから信用情報を取り寄せる方法
信用情報には、過去に契約があった業者名が記載されています。
② 取引していたころの通帳を確認する方法
返済が口座振替の場合、通帳に業者名が記載されています。
クレジットカード会社は通常口座振替での返済です。
③ 可能性のある業者すべてに取引履歴の開示を請求する
①や②の方法で業者名を特定できない場合は、このような方法も考えられます。
これを行った場合、取引がなければ、取引なしとの回答が届きます。
手元に資料が残っていない場合の過払い金返還請求
1 過払い金返還請求の基本的な流れ

過払い金は、例えば、A消費者金融と利息制限法の上限利率を超える貸付利率で継続的金銭消費貸借契約を締結し、それに基づいてある程度の期間借り入れと返済を繰り返していた場合に発生しますが、この過払い金について、A社に対する返還請求を弁護士に依頼しますと、依頼を受けた弁護士は、A社に対して受任通知を送付し、A社と依頼者との間の継続的金銭消費貸借取引にかかる一切の取引履歴の開示を請求します(なお、この取引履歴は契約者ご本人が業者に対して請求することももちろん可能です)。
この取引履歴には、借入れを行った日付と借入金額、および返済を行った日付と返済金額などといった情報が記載されていますので、弁護士は、これらの情報を基に、過払い金の計算用に開発された専用のソフトウエアを利用して、過払い金の金額を算出します。
過払い金の金額の算出が完了しましたら、A社に対してその返還を求める請求書を送付して交渉を開始し、交渉が難航する場合にはA社に対して訴訟提起して、過払い金を回収します。
以上で述べた過払い金返還請求についての流れをご覧いただくとすぐにわかると思いますが、弁護士に依頼して過払い金返還請求の手続きを進める場合、借り入れをしていた業者名が分かれば、契約書やカード等の資料を紛失していても、手続きを進めることが可能です。
2 取引のあった業者がわからない場合
⑴ このように、過払い金返還請求の手続きは業者名がわかれば進めることが可能ですが、業者名について記憶になく、またカードや契約書等の資料も残っていない場合は、別の手段により業者の特定を試みることになります。
まず、消費者金融やクレジットカード会社は、取引のある顧客について必ず信用情報機関に情報を登録し、完済等により契約が終了した後も一定期間その情報は残っていますので、CICやJICCといった信用情報機関から信用情報を取り寄せ、取引のあった業者名が記載されていないかどうか確認するという手段があります。
また、クレジットカードでキャッシングをしていた場合は、返済は通常口座振替で行われますが、口座振替の際には通帳に記録が残りますので、キャッシングをしていた頃の通帳や、通帳がない場合は預金取引明細を銀行の窓口で取得することで、口座振替により返済をしていたクレジットカード会社を特定することが可能です。
⑵ 業者特定の手段としては以上のようなものがありますが、それでも特定が困難な場合は、取引をしていた可能性のある業者すべてについて弁護士に過払い金返還請求を委任し、弁護士から、それらの業者すべてに受任通知を送付するという方法もあり得ます(取引がなければ、受任通知に対して登録なしとの回答が届きます)。
例えば、テレビCMも出している大手消費者金融会社から借り入れをしていたが、業者名がどうしても特定できない場合、アコム、アイフル、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)、新生フィナンシャル(レイク)の4社に受任通知を送付することで、業者を特定できる場合があります。
3 取引履歴が残っていないケース
なお、業者から開示される取引履歴について、例えば、平成6年(1994年)以前の記録は廃棄してしまっているため平成7年以降の履歴のみ開示される、というようなケースがあります(なおこのケースは三菱UFJニコスです)。
このようなケースでは、開示された履歴のみで計算した過払い金を請求することは当然可能ですが、開示されていない部分を含めて計算した場合と比べ、過払い金は当然少なくなります。
このように、業者から開示された取引履歴に不足がある場合でも、記録が残っていれば(例えば返済を口座振替で行っていた場合の通帳の記録など)、未開示部分の取引を推定して計算することで、未開示部分の取引を含めて計算した過払い金の返還を請求できる可能性があります。
以上ご説明しましたとおり、過払い金返還請求は、契約書等の資料が一切ない場合でも、借入れをしていた業者が分かれば可能であり、業者が特定できない場合でも、取引していた可能性のある業者すべてに弁護士から受任通知を送付することで業者を特定し請求することも可能です。
お手元に資料が全くない場合でも、お気軽にご相談いただければと思います。
過払い金返還請求における弁護士法人心の強み
1 過払い金返還請求の難易度

過払い金返還請求とは、消費者金融会社やクレジットカード会社から利息制限法の上限利率を超える貸付利率で借り入れを行い、その利率にしたがって支払った利息について、上限利率超える部分に対応する利息の返還を当該消費者金融等に求める手続きです。
利息制限法の上限利率を超える貸付利率で貸し付けを行い、その利息を借主から受領していた場合でも、改正前の貸金業法はみなし弁済という制度を規定していて、その成立要件を充たしていれば利息制限法の上限利率を超える部分の利息の受領も有効になりましたが、成立要件を充たしていない場合は無効になりました。
このみなし弁済が成立しないことを前提に、支払った利息(利息制限法の上限利率を超える部分)の返還を求める訴訟が提起され、当初は、みなし弁済の成立の有無について激しい争いが展開されましたが、金銭消費貸借契約に期限の利益喪失条項がある場合はみなし弁済の要件を充足しないとした平成18年の最高裁判例の登場により、過払い金返還請求の難易度はぐんと下がりました。
なぜなら、期限の利益喪失条項は、リボ払い等分割での返済を前提とする金銭消費貸借契約にとって必要不可欠と言える条項で、契約条項にこれを定めていない貸金業者はほぼ皆無だったからです(なお、この最高裁判決の後に一部業者は期限の利益喪失条項を削除しましたが、訴訟の勝敗にはほとんど影響は出ていません)。
また、大部分の過払金返還請求については、過払い利息の利率については5%が適用され、この利息が付加されると過払い金の金額も膨れ上がることがありますが、過払い利息は、貸金業者が「悪意の受益者」と認められないと請求できません。そして、「悪意の受益者」については利息を請求する側が主張立証しなければなりませんが、平成19年の最高裁判例は、みなし弁済が成立しない場合は貸金業者は原則として悪意の受益者と推定される、としましたので、利息の請求についても難易度は下がり、争われることは少なくなりました。
貸金業者にとって利息の負担は重く、利息だけで数十万円を超えることもありますので、訴訟前の任意和解では、利息の請求は困難なことが多いです。
2 争点はまだまだ存在します
かつて激しく争われたみなし弁済や悪意の受益者の争点については、一連の最高裁判決により争点としての難易度はかなり下がりましたが、過払い金返還請求については、現在も難易度が高めの争点があります。
従前からよく争われており、現在でも争われることの多い争点として取引の一連性があり、具体的には、取引の途中に貸し借りのない空白期間があった場合や、借り入れた金額に利息を付して1回で返済する1回払い取引を継続していた場合に争点として争われます。また最近では、貸付停止措置が執られた時点を起算点とする消滅時効の主張がなされることが増えており、業者側の主張を認める裁判例も増えています。
このような争点がある場合、同様の争点について一定程度取り扱い経験がある弁護士が担当しないと、解決の見通しを見誤ることや、訴訟での主張立証が不十分になることも想定されます(解決の見通しについて判断を誤ると、同種事案について経験のある弁護士が担当した場合と比べて和解金額が低くなってしまうことも考えられます)。
3 弁護士法人心の弁護士は経験豊富です
弁護士法人心では、設立当初から主力業務として過払い金返還請求事件を取り扱っており、今日に至るまで多数のご依頼を受けていますので、当法人で過払い金返還請求を担当する弁護士はノウハウを蓄積しています。
争点があるケースでも、安心してお任せいただければと思います。
なぜ過払い金が発生するのか
1 利息制限法と貸金業法

お金の貸し借りを法律用語で金銭消費貸借契約といいます。
この金銭消費貸借契約では、とくに金融業者からの借り入れについては、利息が付されることが通常です。
もちろん、利息に上限がないと弱い立場の借主が強い立場の貸主に食い物にされてしまいますので、利息制限法という法律が、貸付利率の上限について定めています。
具体的な上限金利は貸付金額により差異があり、10万円未満の場合は20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%が上限金利となっています。なお100万円を貸し付けた場合(上限金利は15%です)、分割返済により残元金は比較的早く100万円未満になりますが、上限金利は15%のままです。
ところが、改正前の貸金業法は、貸金業法の適用対象となる金融業者について、同法が定める内容を記載した書面を借主に交付するなどの条件を充足すれば、利息制限法の上限利率を超える利率での貸付ができるとしていました(もちろんその利率は青天井ではなく、貸金業法で利率の上限が定められていました)。
この、貸金業法の定める条件を充足した場合の返済は「みなし弁済」と呼ばれ、みなし弁済が成立すると利息制限法を超える部分の利息の収受が適法になりました。
そのため、消費者金融業者やクレジットカード会社の多くは、2007年頃に新規契約者の約定利率を利息制限法の上限利率以下に変更するまで、その上限利率を超過する利率で貸付をしていました(なお、当初から利息制限法の上限利率の範囲内で貸し付けを行っていた消費者金融としてはSMBCモビットがあり、また、オリックス・クレジットは2000年よりも前に利率を上限利率以下に引き下げています)。
このみなし弁済の制度は2010年6月に施行された改正貸金業法により廃止されましたので、現在は、利息制限法の上限利率を超える利率での貸し付けは完全に違法です。
なお、みなし弁済規定が適用されたのは貸金業法による規制の対象である消費者金融会社やクレジットカード会社であり、銀行(銀行法で規制)や信用金庫(信用金庫法で規制)は貸金業法の規制の対象外ですので、これらの金融機関による貸付利率は、古いものでも利息制限法の上限利率以下です(それゆえ銀行からの借り入れについて過払いはありません)。
2 みなし弁済
やや教室事例になりますが、例えば、消費者金融会社が、2000年3月1日に、200万円を、貸付利率25%、返済期限1年後として貸し付けた場合、返済期限の2001年2月28日に返済する利息は50万円となり、元利合計で250万円を返済することになります。
貸付金額が200万円の場合、利息制限法の上限利率である15%で計算すると、50万円の利息のうち30万円を超過する金額(20万円)は、みなし弁済が適用されないとその収受は無効となり、借主は、不当利得として貸主に対し20万円の返還を請求することができます。
この返還を請求する20万円が過払い金と呼ばれるものになります。
このみなし弁済規定ですが、消費者金融会社やクレジットカード会社のほとんどはその適用条件をきちんと守っていなかったため、みなし弁済の適用条件について判断した一連の最高裁判決によって、これらの業者による上限利率を超える部分の利息の収受についてみなし弁済が成立し適法になる余地はほぼなくなりました。
3 過払い金が増大する理由
業者からの借り入れと返済を長期間継続していると、数百万円の過払い金が発生していることも珍しくありません。
このように過払い金が多額になる理由は以下のとおりです。
例えば、消費者金融と極度方式(上限額の範囲で何度でも借り入れができる方式)の金銭消費貸借契約を締結し(約定利率は25%でリボ払いとします)、2000年5月1日に上限額いっぱいの50万円を借り入れたとします。
最初の弁済期日である5月31日に1万5000円を返済したとした場合、約定利率の25%を前提とすると、返済金額のうち1万0273円が利息に充当されますが、利息制限法の上限利率である18%を前提とすると、利息に充当されるのは7397円となり、その差額は2876円となります。
みなし弁済が成立しないと、その2876円が払いすぎた利息、すなわち過払い金となりますが、最高裁判所は、返済によって発生した過払い金について、発生と同時に元金の返済に充当することを認めました。
つまり、約定利率を前提とした弁済後の元金は49万5273円となりますが、上限利率を前提として発生した過払い金を直ちに元金に充当すると、5月31日の時点で元金は49万2397円になります。
しかし、消費者金融会社は、みなし弁済が成立することを前提として、約定利率を前提とした残元金をベースとして約定利率による利息を収受し続けますので、借り入れと返済を長期間継続すると、元金消滅後の返済額も多くなり、過払い金も膨れ上がるのです。
過払い金の請求にかかる期間
1 受任から過払い金の計算完了まで

過払い金返還請求の手続きについてご依頼をいただきますと、弁護士は、まず、対象となる業者に対して受任通知を送付し、取引履歴の開示を求めます。
過払い金の計算には、借入および返済の年月日や金額といった情報が必要になりますが、この取引履歴には、そのような情報が記載されています。
このように、取引履歴は過払い金の計算にあたって重要な資料となりますが、受任通知により取引履歴の開示を請求し、それが実際に開示されるまでの期間は一律ではなく、対象とする業者や取引内容によって異なります。
開示が早い業者は2週間程度で開示されますが、遅い業者ですと2、3か月かかる場合もあります。
取引履歴は郵便またはファックスで開示されるのが通常ですが、開示されましたら、過払い金の計算作業に入ります。
この計算作業には通常、1週間から10日程度の時間が必要になります。
以上をまとめますと、弁護士法人心に過払い金返還請求ご依頼をいただいた場合、過払い金の金額が判明するまでの期間は、取引履歴の開示に要する期間と、計算の作業に要する期間の合計になります。
2 任意交渉
過払い金の金額の計算が完了しましたら、次は過払い金返還請求についての解決方法について検討します。
解決方法には、一般の民事事件と同様に、任意の交渉と訴訟があり、任意の交渉で解決できなければ訴訟に進むことになりますが、過払い金返還請求の場合、業者が任意の交渉と訴訟で和解基準に差を設けているという実態もあるため、任意交渉をスキップして直ちに訴訟を提起することも多くなっています。
特に、確実に争われる争点がある場合や、過払い金の金額(とくに利息の金額)が多く利息も含めた十分な金額の回収を目指す場合は、多くの事案ですぐに訴訟提起しています。
他方、例えば過払い金の金額が比較的少ないなど訴訟に大きなメリットがない場合や、依頼者の方が早期の過払い金回収を希望する場合等は、一般の民事事件と同様に任意の交渉から開始しますが、これについての対応も業者によって区々です。
任意交渉では、まず当方から過払い金の返還を請求する請求書を送付しますが(請求書には2週間程度の回答期限を記載します)、これに対してほぼ期限通りに回答をする業者もあれば、1か月程度何の連絡もない業者もあります(このような業者の場合、電話をしても、まだ担当者が決まっていない等と言われることもあります)。
業者側の回答は、満額回答ということはまずないですので、金額調整の交渉を始めることになりますが、この交渉についても、1回の電話での交渉でまとまることもあれば、何度か電話で交渉し数週間程度かかることもあります。
交渉の内容は基本的に和解金の金額とその返還時期になりますが、この返還時期については、業者によって早かったり遅かったりしますが、和解から3か月後程度になることが多い印象です。
このように、任意交渉での解決を目指す場合、過払い金返還請求書を送付してから過払い金(和解金)が支払われるまで通常5、6か月程度は必要になります。
3 訴訟
訴訟を提起するためには訴状等の書面を作成しなければなりませんが、この書面の準備には1~2週間程度の時間を要します。
訴状等の書類が準備できましたら、管轄の裁判所に訴訟提起をすることになります。訴訟を提起しますと、裁判所から、訴状等の不備について補正を指示する連絡や、第1回期日の調整の連絡がありますが、その連絡までの期間は一律ではなく、裁判所や担当部(担当書記官)によって区々であり、早ければ1週間程度で連絡が来ますが、極端な例では、3週間程度経っても全く連絡がないため当方から確認の連絡をして期日の調整をしてもらう案件もありました。
第1回期日は、通常は1か月から1か月半程度先に指定されますが、年末年始や夏季休廷期間、裁判所の異動時期を挟む場合は、2か月程度先になることもあります。
第1回期日の調整は裁判所と原告の間で行われますが、この第1回期日が決まりますと、裁判所は被告である業者に訴状を送達することになります。
そして、実質的な争点がない事案の場合は、業者が訴状を受領してから第1回期日まで1か月程度ありますので、第1回期日前に業者から和解交渉についての打診があり、交渉の結果、第1回期日前に和解が内定することも多くなっています。なお、和解金の支払期日は和解内定の日から3か月程度先になることが多いです。
業者によっては、第1回期日前は何の連絡もないこともありますが、被告である業者側は、原告の請求について争う場合は遅くとも第2回期日までに反論書面と証拠を提出しなければなりませんので、実質的な争点がなければ、和解困難な業者を除き、第1回期日の1か月後程度に設定される第2回期日までに和解が内定します。
取引の分断など、裁判例でも結論がわかれている争点がある場合は、業者側も特に地方裁判所では弁護士を代理人に選任して対応することになり、そうなりますと、4、5回程度以上の期日が行われることになります。
その場合の解決方法としても、和解になる場合も少なくないですが、双方の溝が埋まらないと判決になります。
以上のとおり、訴訟で解決する場合、実質的な争点がないケースでは、訴訟の提起から和解金の入金まで6、7か月程度は要するものと想定しておく必要があります(なお、実質的な争点がないケースでも和解困難で十分な金額を回収するためには判決が必要になる業者もあり、そのようなケースでは、プラス2か月程度必要になります。また、第一審判決に対して控訴されると、さらに数か月程度の時間がかかることになります)。
重要な争点がある場合はケースバイケースで、訴状提出から第1審判決まで1年程度かかることもあります。
過払い金返還請求を相談する専門家選びのポイント
1 過払い金の存在を知らずに和解

過払い金返還請求は、2006年から本格的に開始し、2009年に返還金額のピークを迎えてそれ以降は徐々に減っていますが、本稿を執筆している2023年時点では、ピークから既に13年以上が経過しているということになります。
2006年から本格化したのは、同年1月13日の最高裁判決(期限の利益喪失特約がある場合の支払いの任意性を否定し、みなし弁済規定の適用を否定した判決)が大きく影響しています。
過払い金返還請求が本格化した2006年の最高裁判決以降は、過払い金返還請求はほとんどの専門家が知るところとなりましたが、それ以前は、過払い金返還請求を知らない専門家も存在し、利息制限法の上限利率で引き直し計算を行えば高額の過払い金が発生するようなケースでも、引き直し計算をせずに約定残債務額をベースとした任意整理(弁済和解)を行ってしまったということが少なからずあったようです。
このように、法律の専門家が代理人として和解を行ってしまうと、錯誤を理由としてそれを無効にするのは困難です。
例えばぎっくり腰で医者(病院)にかかろうと考えた場合、まず内科を受診する人は皆無だと思いますが、弁護士(法律事務所)の場合、相談したい内容と当該弁護士(法律事務所)の専門分野がマッチしているのかどうかについて特に検討することなく法律相談を申し込む方も少なくない印象です。
相談する事項が専門性の高い分野の場合、その分野に弱い弁護士に相談し委任をしてしまうと、上述した過払い金が発生しているケースで弁済和解をしてしまったケースのように、思わぬ不利益を被ることもあり得ますので、十分注意が必要です。
2 現時点ではどうか
過払い金返還請求は弁護士ないし認定司法書士が取り扱う業務分野として定着し、専門家が利用する実務書も複数出版されていますので、現在では、過払い金の存在を知らず引き直し計算をしないまま返済和解の手続きを進めてしまう専門家は皆無だと思います。
また、かつては貸金業者側が厳しく争っていた悪意の受益者などの重要な争点のいくつかは、最高裁判例により解決されました。
ただ、取引に空白期間がある場合の取引の一連性の問題や、貸金業者が貸付停止措置を執った時点を起算点とする過払い金の消滅時効の主張など、訴訟で厳しく争われる争点は現在でも残っています。
そのため、専門家に依頼して過払い金返還請求の手続きを進める場合は、当該専門家の専門分野についての情報を法律事務所のウェブサイト等で探し、過払い金返還請求が重点取扱分野となっているかどうかを確認してみるとよいでしょう。
なお、法律相談で、担当弁護士に対し過払い金返還請求事件についての過去の取扱件数を聞くのももちろん問題ございません。
3 弁護士と司法書士
過払い金返還請求は民事事件となりますので、代理人として過払い金返還請求を受任できる専門家は弁護士と認定司法書士になります。
しかし、認定司法書士は簡易裁判所の民事手続きにおける代理権しか有していませんので、元金が140万円を超える過払い金返還請求については、代理人として活動することはできません。
過払い金の正確な金額は、貸金業者から開示される取引履歴に記載されている情報を基に、表計算ソフトを利用して計算をしてはじめてわかりますので、最初から140万円以上の案件も扱うことができる弁護士に相談することをお勧めします。
過払い金の利息と裁判官
1 過払い金の利息

過払い金が発生し、消費者金融会社やクレジットカード会社がその返還義務を負う場合、過払い金の元金はもちろん、法律上、元金にについて民事法定利率によって算出された利息も付して返還する義務があります。
例えば、2020年1月1日に15年以上継続して借り入れと返済を繰り返していた消費者金融からの借り入れについて完済したので弁護士に過払い金の計算をしてもらったところ、完済時において200万円の過払い金の元金と20万円の利息が発生していた場合は、当該消費者金融会社は、200万円の元金に対して、完済時以降も年5%の利息も付加して返還しなければならないことになります。
このケースで、仮に完済から3年後に過払い金の返還請求を行った場合、返還請求時点においては、完済時までに発生していた利息20万円と完済時以降返還請求時までに発生した利息30万円を合計した50万円の過払い利息が発生していることになります。
民事法定利率は、2020年3月31日までは5%という固定された比較的高い利率になっていたため、取引期間が長く、かつ取引の後半は長期間返済のみを行っていたようなケースでは、引き直し計算をすると最終取引時において既に高額の利息が発生していることも珍しくはなく、この利息のみで100万円を超えるケースもあります。
なお、この過払い金について発生する利息は、厳密には、消費者金融業者等が「悪意の受益者」と認められた場合に返還する義務が発生しますが、最高裁判所の判例により、事実上、貸金業者側が「悪意の受益者」でないことを立証しなければならなくなり、この立証は通常困難ですので、裁判で「悪意の受益者」が否定されることはまずなく、現在ではこの点について本格的に争ってくる貸金業者もありません。
2 和解と過払い金の利息
過払い金の返還請求を貸金業者に対して行う場合、訴訟提起前にまず任意の交渉を行うことが通常です。
ただし、訴訟提起前の任意の交渉では、過払い金の元金をベースにした交渉になることも多く(例えば、過払い金の元金の80%など)、多額の利息が発生している場合は、十分な金額の回収は見込めません。
訴訟を提起した場合は、利息も含めての回収が可能になりますが、訴訟内で和解する場合は(通常は和解で終了します)、和解は当事者双方が譲歩することを前提としますので、争点がないケースでは、過払い金の利息については一部減額して和解することが多いです。
3 過払い金の利息と裁判官
しかし、過払い金返還請求の訴訟をしていると、裁判官を交えて和解の協議が行われる際に、過払い金の元金をベースにその調整を行う裁判官も存在します。
これは、損害賠償など金銭を請求する訴訟手続において和解の協議が行われる場合、元金を基準に当事者双方の調整を行うケースが多く、同じ金銭請求である過払い金返還請求訴訟においても同様に扱おうとするためだと考えられます。
この点、本稿の執筆者は、簡易裁判所の法廷で、裁判官が訴訟代理人である司法書士に対して、「和解で利息まで要求してはいけない。」とも解釈できる発言をしているのを聞き、非常に驚いたことがあります。
これは、元金をベースに和解協議を行う通常の金銭請求の民事訴訟に引きずられた発言だと思われますが、過払い金の返還請求では、まず消費者金融会社やクレジットカード会社が貸付金について高い利率の利息を取っていたという大前提があるのですから、借主側が過払い金の返還を請求する場面においても、過払い金の元金について発生した利息についてある程度返還させる前提で和解の協議を行うのは当然であると言わざるを得ません。
取引の一連性の争点
1 古典的争点

取引の一連性の有無については、過払い金返還請求訴訟において古典的な争点で、現在でも貸金業者から本格的に争われることがあります。
この取引の一連性の有無の争点には複数のパターンがありますが、ここでは、極度額の範囲内で何度でも借り入れができる継続的な金銭消費貸借取引において、途中、取引がなく残高が0円になっている期間(これを実務上「空白期間」といいます)がある場合に、その空白期間を挟んだ前後の取引を一つの取引とみなして過払い金の計算をすることができるか否か、という争点についてご説明します。
空白期間を挟んだ前後の取引を一つの取引(これを実務上「一連の取引」といいます)として計算する場合、過払い金の金額も大きくなることが通常ですし、消滅時効の起算点も原則として空白期間の後に開始した取引の最終取引日となるというメリットがあります(仮に一連の取引として計算できないと認定された場合は、空白期間前の取引が一個の独立した取引となりますので、その取引で生じた過払い金の消滅時効は、その取引の最終返済日になります)。
2 2つのパターン
貸金業者との継続的金銭消費貸借取引に空白期間があるケースには、大きくわけて2つのパターンがあります。
一つ目のパターンは、空白期間前の取引について貸金業者と締結した継続的金銭消費貸借契約(これを「基本契約」といいます)をそのまま利用して空白期間後に借り入れを再開したケースです。
クレジットカード会社のキャッシングの場合、クレジットカードはショッピングにも利用することができ、基本契約であるクレジットカード契約そのものを解約する(=当該業者のクレジットカードの利用を止める)ことは滅多にないですので、このケースが多くなっています。
二つ目のパターンは、空白期間の前後で基本契約が異なる場合、すなわち、完済に伴い基本契約を解約したものの、その後当該業者と新たな基本契約を締結して借り入れを再開したケースです。
消費者金融からの借り入れの場合は、完済に伴い基本契約を解約する方も少なからずいらっしゃいますので、このケースも多くなります。
空白期間前後の取引が同一の基本契約に基づく場合は、空白期間の長さに関わらず、原則として空白期間前後の取引は一連の取引となります。
ただし、形式的には基本契約は同一でも、実質的に見ると別々、すなわち新たな基本契約を締結して借り入れを再開したと言えるような場合は、例外的に一連性が否定されることもあります。
例えば、空白期間が相当長期間にわたる場合は、形式的には当初の基本契約が維持されていたとしても、取引を再開する際に与信審査やカードの再発行等が行われていることも多いですので、このようなケースでは、実質的には新たな基本契約を締結して借り入れを再開したと認定されることも多いでしょう。
他方、空白期間前後で基本契約が形式的にも異なる場合は、原則として取引の一連性は否定されます。
ただし、空白期間が比較的短期間で、空白期間前後の各基本契約の内容(貸付利率、貸付極度額や返済方法等)が同一ないし類似しているというような事情がある場合は、例外的に、一連の取引と認定されることがあります。
取引の一連性の判断には専門的知識が必要となりますので、ご自身で判断することはせず、詳しくは弁護士にご相談ください。
過払い金返還請求をするメリット・デメリット
1 はじめに

過払い金返還請求とは、利息制限法の上限利率を超える貸付利率で貸し付けを受け、その貸付利率で計算された利息を支払った場合に、利息制限法の上限利率を超える部分に対応する利息について、消費者金融やクレジットカード会社から返還してもらう手続きです。
貸金業者による貸し付けは、かつて規定されていた「みなし弁済」の要件を満たしていれば、利息制限法の上限利率を超える利率による利息の収受も適法とされていましたが、最高裁判所の判決により、貸金業者の実務慣行を前提とするとみなし弁済の成立は極めて困難となったため、過払い金返還請求が隆盛となりました。
なお、5万円の商品を購入し銀行振り込みで代金を支払ったところ、金額を勘違いして6万円を振り込んでしまった場合、買主に対して払いすぎた1万円の返還を求めることになりますが(これを不当利得返還請求といいます)、過払い金返還請求も、法律的にはこれと同一です。
払い過ぎたお金を返してもらう、という極めて明快な請求ですので、そのこと自体にデメリットというものはありません。
むしろ、お金の返還を受けるのですから、返還された金銭を生活費や他の借金の返済に充てたりすることができるというメリットがあります。
消費者金融会社やクレジットカード会社と長期間継続して金銭消費貸借取引を行っていると、過払い金は数百万円以上に膨らむこともありますので、回収した過払い金で自動車を購入した方もいるようです。
2 デメリット
このように、過払い金返還請求は払いすぎた金銭を回収する手続きですので、請求そのものには基本的にデメリットはないですが、対象業者に対する負債の状況によっては、請求により信用情報についてデメリットが生じる可能性があります。
信用情報について生じうるデメリットをご説明するにあたり、まず、過払い金を請求する際の、対象業者に対する負債の状況について3パターンを区別します。
① 対象業者に対する負債が一切ないケース(過払い金の対象にある金銭消費貸借取引について完済しており、かつ、ショッピング取引等の負債も一切ないケース)。
② 過払い金の対象になる金銭消費貸借取引について、約定残債務(約定利率を前提、すなわち利息制限法の上限金利による引き直し計算前の債務額)があるケース。
③ 過払い金の対象となる金銭消費貸借取引以外の取引(ショッピング取引等)について残債務があるケース
まず、①のケースについては、対象業者に対する負債は一切ないですので、信用情報に事故情報が登録される理由はなく、問題は生じません。
②のケースは、利息制限法の上限利率で引き直し計算をすると約定残債務は完済、ということになりますが、それまで継続していた約定残債務の返済をいったんストップしますので、業者によっては、一時的に信用情報に事故情報を登録しているようです。
この場合、例えば他社のクレジットカードの利用ができなくなるというようなデメリットが発生する可能性があります。
③のケースは、発生している過払い金からショッピング取引等の負債を控除して(これを法律用語で相殺といいます)返還を受けることになります。つまり、実質的には返還を受ける過払い金の一部をショッピング取引等の負債の返済に充てるということになり(任意整理)、また、過払い金を請求するにあたりショッピング等の負債の返済をストップしますので、信用情報に事故情報が登録されるものと思われます。
このように、対象業者に対する負債の状況によっては、過払い金返還請求により信用情報に事故情報が登録されてしまうケースがありますので、手続きを進めるにあたっては、このデメリットの影響について弁護士とよく相談することが重要となります。
過払い金返還請求のご依頼はお早めに
1 過払い金についてのご相談の傾向

過払い金返還請求のご相談は、数としては減少傾向にありますが、過払い金が発生していない方からのご相談は相対的に増えてきている印象があります。
みなし弁済を廃止する貸金業法の改正に対応するため貸金業者が新規契約者に対する貸付の利率を利息制限法の上限利率以内に引き下げてから10年以上が経過しており、また、2010年9月に武富士が激増する過払い金返還請求に耐えかねて会社更生法の適用を申請したことがマスコミで報道されたことにより過払い金の存在が広く知れ渡ったため、過払い金が発生する高い利率での借り入れをしていた方の多くは、既に過払い金の請求を行い返還を受けているものと思われます。
2 過払い金が発生している方の現在の相談の傾向
⑴ 完済するまで返還請求を控えているケース
約定利率による債務(約定残債務といいます)が残っている場合でも、利息制限法の上限利率で引き直し計算を行うと過払いになっていることはよくあります。
ただ、約定利率による債務が残っている場合は、その段階で返済を停止して過払い金返還請求を行ってしまうと、一時的であっても信用情報に影響を与えてしまう可能性があります。
そのため、過払い金のご相談では、約定残債務を完済するまで過払い金の請求を控えていたという方が少なからずいらっしゃいます。
たしかに、今後審査が最も厳しい住宅ローンを組む予定がある場合や、日常生活や仕事でクレジットカードの利用が必須であるという場合は、約定残債務を完済して契約を終了し、信用情報との繋がりを切断してから請求する方が安全です。
しかし、最近は、過払い金返還請求権の時効について最後取引日から10年(改正前民法が適用されるケース)とは言えないケース(貸付停止措置が執られた日から消滅時効期間が進行するケース)も現れてきており、また、取引の分断があると分断前の取引で生じた過払い金が時効になる可能性もありますので、過払い金返還請求を遅らせると、時効により請求ができなくなるリスクが増えるということにもなりかねません。
そのため、完済まで返還請求を控える場合は、弁護士にも相談し、そのメリットとデメリットをよく検討する必要があります。
⑵ 過払い金は約定残債務を完済してはじめて請求できると誤解しているケース
過払い金は約定残債務を完済しないと請求できないと誤解している方は時々いらっしゃいます。
この点は、まず法律の専門家が正しい情報を提供することで一般の方々の誤解を解消するよう努めなければなりませんが、誤解したまま完済まで過払い金返還請求を控えていると、⑴と同様のリスクが生じます。
なお、以上と同種の誤解ですが、例えば、約定残債務が20万円の時に弁護士に過払い金返還請求を依頼し、弁護士が計算した過払い金の金額が100万円だった場合、返還請求できるのは80万円であると誤解している方もいらっしゃいます。
過払い金の引き直し計算は、計算完了後も債務が残っている場合は過払いではなく、逆に過払いが発生している場合は、債務はゼロ(過払い金によって完済されたということです)になります。
ただし、過払いの対象となる取引以外の取引について債務がある場合は、計算完了後の過払い金と相殺されることになります。
⑶ 過払い金についての弁護士への依頼をためらっているケース
例えば、多くの消費者金融やクレジットカード会社が利息制限法の上限利率を超える利息を取っていた2000年から2005年ころから消費者金融等と10年以上取引しており、ほぼ確実に過払い金が発生していると考えられるケースでも、まず過払い金があるかどうかだけチェックしてほしい、という方がいらっしゃいます。
このような方々は、過払い金の返還請求そのものを依頼してしまうと、仮に過払い金が発生していなかった場合、弁護士費用を支払うことで持ち出しになってしまうという誤解を持っているようです。
弁護士法人心では、過払い金返還の依頼を受けたものの、調査の結果過払い金がなく(例えば利率が下がってから取引を開始していたようなケース)、または極少額で業者への返還請求が困難であった場合でも、ご依頼者の方の収支がマイナスにならないよう可能な限り配慮しています。
過払い金のチェックのみ依頼を受けた場合、弁護士は、その時点では過払い金返還請求についての代理人ではなく、業者に対し代理人として過払い金返還の催告を行うことはできません。
仮に消滅時効期間の満了が迫っていた場合、過払い金返還請求そのものの依頼をしていなかったために、消滅時効期間が経過して請求できなくなってしまった、というデメリットも生じかねません。
そこで、過払い金については、過払い金返還そのものを依頼いただくことをお勧めします。
過払い金が生じないケース
1 過払い金の相談

最大手の消費者金融会社であった武富士が東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請したのは2010年9月で、これにより過払い金というものの存在が広く知れ渡り、消費者金融やクレジットカード会社から借り入れをしていた多くの方が過払い金返還請求の手続きを行いましたが、現在でも、件数は大きく減少したものの、過払い金についての相談を受けることが時々あります。
一方、過払い金が発生しない取引について過払い金の相談をお申込みになる方は増加しているという印象を受けています。
そこで、本項目では、これまでにご相談を受けた過払い金が発生しないケースについてご紹介します。
2 利息制限法の上限利率以下での貸付けのケース
⑴ 利息制限法の上限利率を超える利率で貸付を行っていたのは、みなし弁済を規定していた当時の貸金業規制法が適用される消費者金融会社とクレジットカード会社ですが、そのほとんどは、今から15年以上も前である2008年頃までには新規契約者に対する貸付の利率を利息制限法の上限利率以下に変更しました。
過払い金の発生は、利息制限法の上限利率を超える利率で計算した利息の支払いが前提となりますので、消費者金融会社等が新規契約の貸付利率を下げた後に当該会社と新たに契約を締結して借り入れ(キャッシング)を開始した場合は、過払い金が発生することはあり得ません。
なお、借入金を完済している場合は、とくに消費者金融の場合は契約書の返却を受けていると思いますが、その契約書が契約当初のものであり、かつ、貸付利率として利息制限法の上限利率以下(上限利率は、極度額が10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%です)の利率が記載されている場合は、当該契約に基づく貸し借りは過払い金が発生する取引ではないことがわかります。
⑵ 貸金業法で総量規制が導入されて以降、総量規制が適用されない銀行のローン(カードローン)が隆盛となっていますが、銀行ローンの貸付利率は、古いものであっても利息制限法の上限利率以下ですので、過払い金は発生しません。
みなし弁済を規定していた貸金業法(当時は貸金業規制法と呼ばれていました)が適用されるのは消費者金融会社やクレジットカード会社で、銀行に適用されるのは貸金業法ではなく銀行法ですので、銀行は利息制限法の上限利率内での貸付けしかできません。
⑶ 利息制限法の上限利率を超える利息の受領を適法とするみなし弁済規定が適用される消費者金融会社でも、当該規定が廃止される前から利息制限法の上限利率内での貸付けのみ行っていた業者があります。
モビット(現SMBCモビット)はそのような業者の一つですが、契約が古くても貸付利率は利息制限法の上限利率内ですので、モビットとの取引で過払い金が発生することはありません。
⑷ クレジットカード会社の場合でも、みなし弁済廃止前から利息制限法の上限利率内での貸付を行うキャッシングを提供していた会社もありますので、そのようなキャッシングを利用していた場合は、過払い金は発生しません。
ただ、大手クレジットカード会社には複数の業者が合併等してできた会社も多いため、一つの業者に対し利息制限法の上限利率を超えるキャッシング取引と超えないキャッシング取引が併存しているケースもあります。
3 立替金(ショッピング)取引について
クレジットカードのショッピング取引、またはショッピングクレジットを利用した商品購入は、クレジットカード会社ないし信販会社が取り扱っていますが、その返済方法がリボ払であっても過払い金は発生しません。
ショッピング取引のリボ払いに適用されるのは割賦販売法で、貸金業法(旧貸金業規制法)ではないからです。
消費者金融の取引履歴の読み方
1 取引履歴とは

弁護士は、任意整理または過払い金返還請求の依頼を受けた場合、消費者金融会社やクレジットカード会社に受任通知を送付し、継続的金銭消費貸借取引(キャッシング取引)にかかる取引履歴の開示を請求します。
この取引履歴には、借入日・返済日や借入金額・返済金額などが記載されています。
この取引履歴は、弁護士のみが請求できるというわけではなく、消費者金融会社やクレジットカード会社と契約している方はどなたでも請求することができます。
ただし、契約者ご本人が請求する場合と、弁護士が請求する場合では、取引履歴の書式が異なることがあり、弁護士に開示される取引履歴の方が過払い金の計算がしやすい場合もあります。
2 消費者金融会社の取引履歴
消費者金融会社の場合、契約日、借入日、借入金額、返済日、返済金額、約定利率などの情報が記載されています。
記載されている項目は業者によって区々ですが、最大手であるアコム株式会社の場合、契約日、借入日・借入金額、返済日・返済金額、次回返済期日、約定利率・損害金利率、契約解約日、取引方法(店頭またはATM)など、多くの項目が記載されており、どのような取引が行われたのかをある程度読み取ることができます。
例えば、取引の途中で残高がゼロになっている場合、取引の分断について検討する必要があります。
この場合、金銭消費貸借の基本となる契約、すなわち基本契約が途中完済の前後で同一かどうかが重要なポイントとなりますが、アコムの場合、基本契約が解約されると取引履歴に「解約」と表示されますので、基本契約が解約されたのかどうかがすぐにわかります。
また、アコムは契約途中で利率を一方的に下げていることがありますが(例えば25%→18%)、約定利率が例えば18%から0%になっている場合は、返済が厳しくなった等の事情により、業者と契約者の間で返済条件を変更する合意が行われた可能性があります。
このようなケースでは、過払い金を請求するにあたり、その合意(和解)が無効かどうかが争点になります。
なお、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の場合、契約者ご本人が請求した場合(または弁護士が取引履歴の請求のみ受任して請求した場合)の取引履歴には約定利率の変遷が記載されていますが、弁護士が任意整理または過払い金返還請求を受任して請求した場合は記載されていません。
そのため、過払い金返還請求を受任した弁護士は契約時から最終取引日に至るまでの約定利率の変遷を同社に問い合わせる必要がありますが、過払い金返還請求に慣れていない弁護士の場合、約定利率を確認せずに利息制限法の上限利率で引き直し計算をしている場合がありますので、注意が必要です(SMBCコンシューマーファイナンスの場合、契約極度額が10万円以上100万円未満のケースで、利率を18%未満に下げていることがあります)。
貸金業者との和解の勧誘に応じる前に弁護士にご相談を
1 消費者金融会社の苦慮

利息制限法の上限利率を超える利率で貸し付けていた消費者金融会社やクレジットカード会社は、2010年6月にグレーゾーン金利が廃止されるということもあり、多くの業者が、2006年ころから2008年ころに、新規契約者に対する貸付利率を利息制限法の上限利率以下に引き下げました。
また、グレーゾーン金利で借り入れを行いまだ完済していない利用者の約定利率も、時期は利用者により区々ですが、業者により利息制限法の上限利率以下に下げられています。
しかし、約定利率を利息制限法の上限利率以下に下げたとしても、グレーゾーン金利による利息を長期間収受していた場合はあまり意味がありません。
例えば、引き直し計算をすると利息も含めて100万円の過払い金が発生しているという場合、その状態で業者が50万円を追加で貸付けたとしても、計算上は、100万円の過払い金からすぐにその返済に充てられますので、貸し付けた50万円について業者は約定利率分の利息を取ることはできません。
つまり、引き直し計算をすると既に過払いになっている利用者に対して追加で貸付けを行っても、実質は過払い金の返還であり、、将来過払い金の返還を請求されると、業者は利息収入を確保することはできません。
そこで、総量規制が導入されたこともあり、計算上過払い金が発生している利用者については、追加の貸付けを停止している例も見られます。
2 和解の勧誘に注意
このように、引き直し計算をすると過払いになっている利用者に対して追加の貸付けを行っても、将来過払い金の返還を請求された場合は、利息収入を確保することはできませんので、追加の貸付けを停止している例が見られますが、それを超えて、返済についての和解の勧誘を行って和解を締結している例も見受けられます。
例えば、約定残債務(引き直し計算前の残高のことです)が200万円の場合、約定利率が利息制限法の上限である15%に引き下げられていた場合でも、多額の利息が発生しますので、完済までは長期間かかります。
そのような利用者に対し、業者が、優良顧客だからサービスで利息を0%にできますなどと声をかけ、返済条件を変更する内容の和解の締結を勧誘しているケースがありますが、引き直し計算をすると多額の過払い金が発生していた場合、その和解契約の内容によっては、過払い金の請求が困難になるおそれがあります。
業者から表面的には有利な内容の和解の勧誘をされた場合は、それに応じる前に必ず弁護士に相談してください。
引き直し計算の注意点
1 引き直し計算とは

引き直し計算とは、利息制限法の上限利率を超える利率で借り入れを行っていた場合に、利率を上限利率に変更して計算し直すことをいいます。過払金を算出するためにはこの引き直し計算が必要ですが、引き直し計算を行うためのエクセルソフトはネット上から無料でダウンロードすることができ、そのエクセルソフトに消費者金融業者やクレジットカード会社から開示された取引履歴に記載されている情報(借入日と借入金額、返済日と返済金額等)を入力することにより過払い金を算出することになります。なお、過払い金が生じていない場合でも、このエクセルソフトへの入力により、利息制限法の上限利率を前提とした残高を計算することができます。
以下では、この引き直し計算を行う際の注意点について、何点か指摘したいと思います。
2 入力漏れ、入力間違い
消費者金融やクレジットカード会社との継続的な金銭消費貸借取引では、利用限度額の範囲で借り入れと返済を繰り返すのが普通で、その取引期間が10年以上になることも珍しくありません。
そうなりますと、エクセルソフトに打ち込まなければならない文字数も膨大になります。
消費者金融等から開示される取引履歴の中には、文字が小さいものもありますので、見間違うこともあり得ますし、エクセルソフトでは貸付けと返済は入力する列が異なりますので、例えば誤って貸付を返済欄に入力してしまうこともあります。
入力後は、入力したエクセルの表をプリントアウトし、入念にチェックすることが重要です。
3 利率の入力
エクセルには、借り入れと返済の日付および金額の情報のほかに、適用する利率も入力します。
利息制限法の上限利率は、貸付金額が10万円未満の場合は20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%になります。ただし、利用限度額の範囲で借り入れを繰り返す取引の場合、1万円ずつ借り入れて残高が10万円になった時点で、上限利率は20%から18%に切り替わることになりますので、エクセルの利率も変更する必要があります。
また、利用限度額が100万円で、エクセルでの計算上10万円以上100万円未満で推移していた残高が、利用限度額の引き上げに伴う借り入れの増加により100万円以上になった場合はその時点で上限利率は15%になりますが、その後返済により残高が100万円未満になったとしても、上限利率は15%のままになります(18%に戻るわけではありません)。
取引開始当初は利息制限法の上限利率を超える取引であった場合でも、取引の途中から利息制限法の上限利率未満の利率になっている場合がありますので、そのようなケースでは、約定利率が利息制限法の制限利率を下回った時点でエクセルに約定利率を入力することになります。
この操作については、専門家でも忘れることがありますので注意が必要です。
ただし、利息制限法の上限利率未満の利率になった時点では既に過払いになっていることも多く、その場合は貸付利率は問題になりませんので(発生している過払い金に法定利率による利息が付加されます)、利息制限法の上限利率のままにしてしまっていても、計算結果は同じになります。
過払い金返還請求を弁護士に依頼する時期
1 過払い金が発生していれば請求できます

利息制限法は金銭の貸付を行う際の利率についてその上限を定めていますが、この上限を超える利率で消費者金融会社やクレジットカード会社と継続的に借り入れおよび返済を行っている場合(取引期間中一部の時期のみ利息制限法の上限利率を超えている場合も含みます)、現時点で借入残高があったとしても、利息制限法の上限利率に引き直して計算をするとその残高が消滅し、過払い(払い過ぎということです)になっていることがあります。
過払い金が発生していれば、すなわちお金を払い過ぎていれば、当然ですが、その払い過ぎた金額について返還を請求することができます。
なお、残高があると(または残高を全額返済しないと)過払い金の請求ができない、と誤解されている方も時々いらっしゃいます。
しかし、過払い金が発生している=その残高はもうない、ということになりますので、利息制限法の上限利率に引き直して計算し過払い金が発生していれば、その返還を請求することができます。
また、クレジットカード会社については、キャッシングまたはローンとは別にショッピングの残高が残っている場合があります(なおショッピング取引に過払いはありません)。この場合、ショッピングの残高より過払い金の額の方が大きければ、ショッピングの残高を控除した金額を請求することができます(これを法律用語では相殺といいます)。
2 過払い金の返還請求手続を弁護士に依頼する時期―信用情報との関係
借入金について既に完済していて新たな借り入れはなく、またクレジットカード会社の場合はショッピングの残高もなければ、すぐに過払い金返還請求を弁護士に依頼していただいて問題ありません。
しかし、借入金について約定残高(利息制限法の上限利率に引き直して計算する前の残高)がある場合や、ショッピング取引について残高がある場合は、弁護士が過払い金返還請求の代理人として業者に受任通知を送付すると、信用情報に事故情報が登録されてしまうことがあります。
なぜなら、借り入れの約定残高やショッピングの残高について、いったん返済をストップすることになるからです。
もちろん、このような場合でも、過払い金返還請求について業者側との和解が成立した場合は(または過払金返還請求訴訟の判決が確定した場合は)、約定残高やショッピングの残高は和解や判決により確定的に消滅しますので、信用情報では完済となりますが、日常生活でクレジットカードの利用が必須の方や、住宅ローンの利用を検討している方の場合は、対象業者に対する負債のすべてを完済し、クレジットカード契約等を解約してから過払い金返還請求を弁護士に依頼した方が安全でしょう。
ただし、過払い金返還請求を行う時期を遅らせる場合、取引の分断や貸付停止措置という争点との関係で消滅時効の問題が発生することもありますので、完済する前に一度弁護士に相談し、場合によっては取引履歴のみ業者から取得して確認しておくとよいでしょう。
過払い金には消滅時効があるためお早めに弁護士にご相談ください
1 過払い金の消滅時効

過払い金は、法律的には不当利得返還請求権(過払金返還請求権)という債権になるため、債権として10年の消滅時効が適用されます。
なお、消滅時効については令和2年4月1日から施行された改正民法により消滅時効期間等について改正がなされましたが、令和2年3月31日以前に消滅時効期間が開始している過払い金(令和2年3月31日以前に完済しているケース等です)には改正前民法が適用されますので、ここでは改正前民法が適用されるケースを前提にご説明します。
2 過払い金の消滅時効の起算点
過払金返還請求権の消滅時効の起算点(消滅時効期間のカウントが始まるスタート時点のことです)については最高裁判所の判決があります。その判決要旨は、「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が、借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払い金が発生したときには、弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払い金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は、上記取引により生じた過払い金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り、上記取引が終了した時から進行する」という内容です(最高裁HPの裁判要旨)。
つまり、消費者金融からの借り入れやクレジットカードのキャッシングのように、基本となる契約に基づいて借り入れと返済を繰り返す取引の場合、「取引が終了した時」から消滅時効期間が進行することになりますが、これは、約定残高を完済していたときは完済の時、完済する前に返済をストップしていたときは最後の取引時(最後の取引が借り入れということもあり得ます)であると一般に考えられています。
このように考える根拠として、最高裁は、過払い金が発生した時点から時効期間が進行すると、借主は取引終了時ではなく過払い金が発生したときにその返還を請求しなければならず、そうなると借主に継続的金銭消費貸借を終了させること(=新たな借り入れができなくなること)を強制することになるという点を挙げています。
3 お早めに弁護士にご相談ください
この最高裁の判断を敷衍すると、取引の途中でも、新たな借り入れがあり得ないような事情が生じた場合には、新たな借り入れに対する借主の期待を保護する必要はなくなるため、その時点から消滅時効が進行する、という解釈も可能になります。
貸金業者側は、新たな借り入れがあり得なくなった事情として貸付停止措置(借入限度額を0円とすることです)を取ったということを挙げ、その措置を取った時点から消滅時効が進行すると主張してくることがあります。
この主張についての最高裁の判断はなく、高裁以下の裁判例の結論は分かれていますが、ここで注意が必要なのは、今現在も返済を継続している、または完済からそれほど時間が経っていないケースでも、10年以上前に貸付停止措置が執られていた場合は、10年前までに発生していた過払い金について消滅時効を主張される可能性があるということです。
時効は取引終了から10年と安易に判断することはせず、過払い金についてはお早めに弁護士にご相談ください。
過払い金返還請求における一連計算の争点について
1 はじめに

消費者金融やクレジットカード会社に対する過払い金返還請求が隆盛になったのは2000年代の後半ですので、それ以降既に10年以上が経過していることになります。
この間、裁判で争われる件数も多かったですので、最高裁判所や下級審裁判所(高等裁判所、地方裁裁判所、簡易裁判所)の判決によって、過払い金返還請求に関する争点についての判断が多数示されてきました。
最高裁判所による判決で有名なものの一つは、悪意の受益者の争点についての平成19年7月17日判決です。
この判決により、貸金業者等は原則として悪意の受益者であると推定される、とされました。
そのため、一部の消費者金融業者は、悪意の受益者であるとの推定を覆すため、ATMジャーナル等の大量の証拠を提出して争ってきていましたが、下級審判決の大半は、消費者金融業者は悪意の受益者であると認定し、また一部の業者については最高裁判決によって悪意の受益者とされたため、現在では、裁判で悪意の受益者が争点となることはほとんどありません。
なお、貸金業者等が悪意の受益者とされた場合、発生した過払い金に5%の利息が付されますので(ただし改正民法が適用される事案の場合は3%になります)、場合によっては利息だけで何十万円にもなり、業者にとっては重い負担となります。
ここでは、現在でも争われる一連計算の争点についてご紹介します。
2 一連計算について
いわゆる一連計算と言われる争点にもいくつかの類型がありますが、ここでは、事案も多い2つの類型を紹介します。
まず、ケースも多く貸金業者等からよく争われる類型は、利用限度額の範囲内で何度も借り入れが可能な継続的金銭消費貸借の取引で、取引の途中でいったん完済している類型です。
例えば、利用限度額50万円の契約で平成10年4月1日から借り入れを開始し、平成17年3月31日にいったん完済したものの、平成17年12月1日に再度借り入れをして取引を再開した、というケースです。
このケースの場合、完済の前後の基本契約が同じかどうかによって判断の枠組みが異なります。
その判断枠組みは最高裁判決によって示されていますが、とくに完済の前後で基本契約が異なっている場合は、一連計算が認められるためにはいくつかの要件を充たす必要がありますので、訴訟においてもその要件の充足の有無を巡って激しく争われることがあります。
次に、一回払取引について一連計算が可能かどうかという争点があります。
クレジットカード会社のキャッシングの場合、主な返済方式としてリボ払いと一回払いがあり、一回払いの場合、一つの借り入れに対する返済は一回で完了します。
例えば、ある月の1日から月末までに借り入れた金銭については翌々月の15日に利息を付して一括で返済する、というような取引です。
この一回払取引を基本契約に基づき繰り返し行った場合に、それぞれの一回払取引を一つの取引として一連計算できるかどうかが争われます。
この争点については、最高裁判所の判決はなく、高裁判決も判断は分れています。