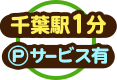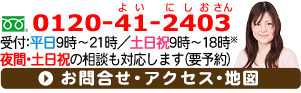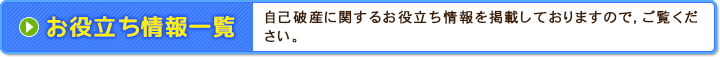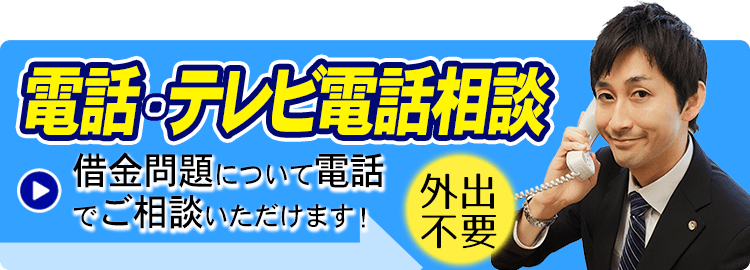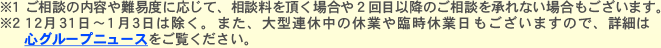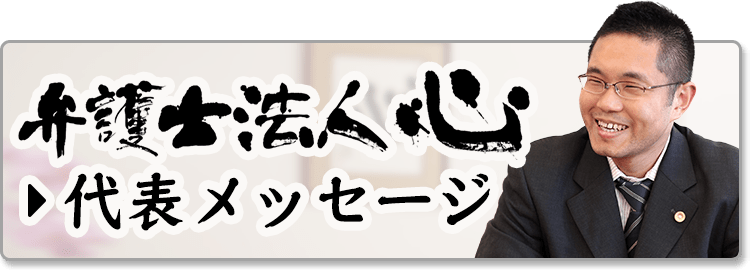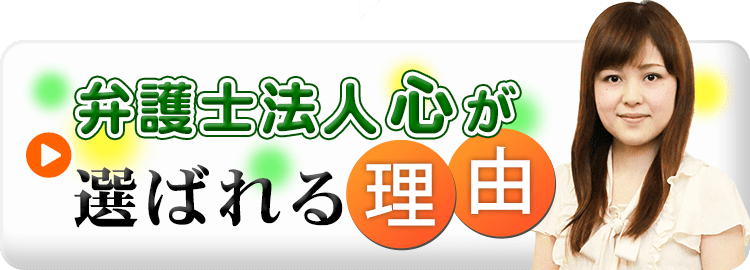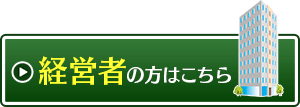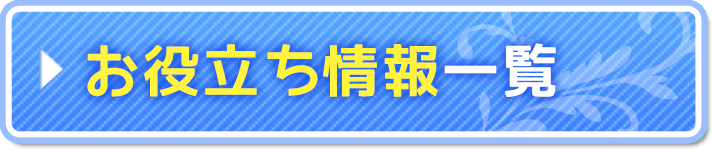Q&A
滞納していた税金は自己破産をするとどうなりますか?
1 非免責債権
免責を許可する決定が確定すると、破産者は、原則として破産債権全部について、弁済する責任を免れることになります。
しかし、破産法は、免責を認めるのが相当でない債権について、免責の対象から除外しています(253条1項)。
例えば、破産法253条1項2号は、破産者が悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償債権について、非免責債権としています。
例えば、会社で経理を担当している従業員が、会社の経費1億円を横領したケースについて考えてみます。
この従業員は、横領した1億円に、遅延損害金を加算した金額を会社に賠償する責任が発生します。
これは、悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償債権となります。
そのため、破産手続で免責を許可する決定を受けても、賠償する責任を免れることはできません。
また、破産法253条1項3号では、破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権も、非免責債権としています。
例えば泥酔状態で車を運転し死亡事故を起こした場合には、重大な過失による事故であると言うことができます。
そのため、免責が許可された場合にも、死亡事故についての損害賠償責任は免除されません。
2 破産法253条1項1号
破産法253条1項1号は、租税等の請求権を非免責債権として規定しています。
租税等の請求権とは、国税徴収法または国税徴収の例によって徴収することのできる請求権です。
「租税」というと、住民税(市県民税)や固定資産税、自動車税といった税金だけを思い浮かべる方も多いと思います。
しかし、国民健康保険料や国民年金保険料も租税等の請求権に該当しますので、免責決定により免責されることはありません。
また、下水道利用料金も国税徴収法または国税徴収の例によって徴収することのできる請求権に該当しますので、免責されません。
ただし、上水道料金は通常の破産債権ですので、破産開始決定時に滞納していた上水道料金は、免責決定により免責されます。
このように、税金等は破産手続を行っても免責されません。
そのため、弁護士に自己破産を依頼した後は、できるだけ早く役所へ行き、分割納付をするために相談してください。
2回目の自己破産をすることは可能ですか? 自己破産の免責とはなんですか?