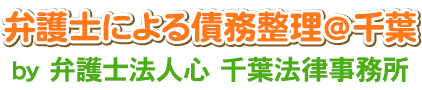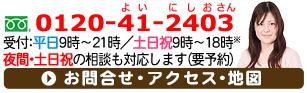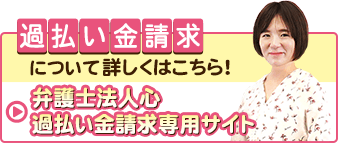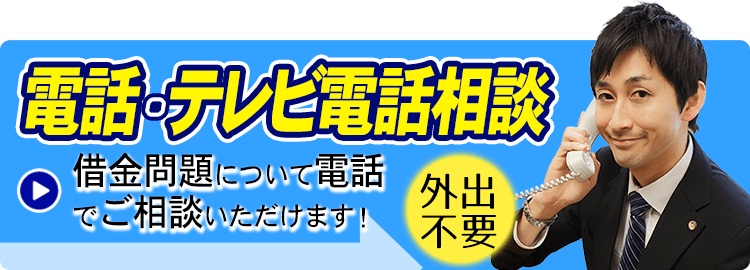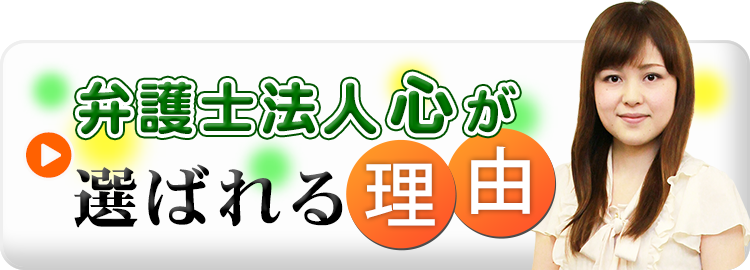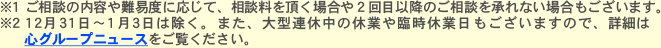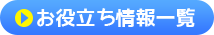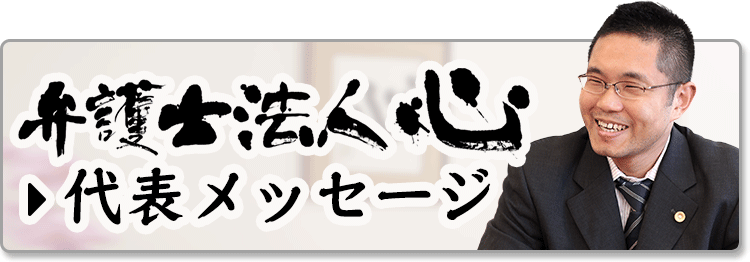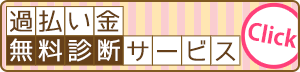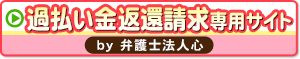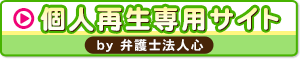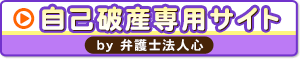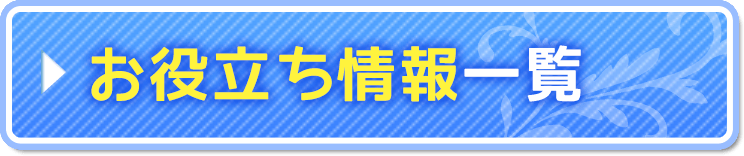過払い金返還請求のご相談をお考えの方へ

1 過払い金返還請求は弁護士に相談を
長い間返済を続けるうちに、過払い金というお金が発生している場合があります。
過払い金と言うのは返しすぎたお金であり、過払い金返還請求をおこなうことにより取り戻すことができる可能性があります。
過払い金返還請求をスムーズにおこない、適切な金額を取り戻すためにも、弁護士にご相談ください。
2 過払い金を無料で診断するサービスをご用意
過払い金という言葉を耳にしたことがあったとしても、「自分の場合は過払い金が発生しているのだろうか…」と悩み、弁護士に相談すべきかどうか決断できずにいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に気軽にご利用いただけるように、過払い金の金額を無料で計算するサービスをご用意しています。
こちらのサービスを利用して過払い金の金額を確認し、弁護士に依頼するかどうかの判断材料にしていただくことができます。
3 弁護士へのご相談は原則無料
また、過払い金のご相談を原則無料で承っておりますので、過払い金について詳しく知りたいという方や、過払い金返還請求を行った場合の見通しについて知りたいという方などは、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
過払い金返還請求などの借金に関する案件を得意とする弁護士がご相談に対応させていただきます。
過払い金の電話相談
すでに返し終えている借金について過払い金返還請求をおこなう場合,手続きなどもすべてお電話と郵送でしていただくことができます。まずはご相談をお申し込みください。
過払い金の計算方法と具体例
1 過払い金の計算方法

過払い金の計算方法については、かつては、貸金業者側は貸金業者に有利な方法、過払い金の債権者側は債権者に有利な方法を主張し、対立していましたが、現在では、その対立のほとんどは最高裁判決によって解決されています。
本稿では、最高裁判決を前提として、過払い金の計算方法についてご説明します。
2 過払い金とは
ここでの過払い金とは、払いすぎた利息のことを指します。
利息制限法は、金銭の貸し付けについて上限利率を定めていますが、かつては、一定の要件(「みなし弁済」と言います。)を満たせばこの上限利率を超える金利での貸付をすることができました。
しかし、一連の最高裁判決によって、この一定の要件の充足が否定されましたので、収受した利息のうち上限利率を超える部分が過払い金となったわけです。
例えば、100万円を返済期日1年後、利率20%で貸し付けた場合、利息制限法の上限利率は15%になりますので、1年後に収受した20万円の利息のうち5万円が過払い金となります。
3 元金が残っている場合
上記は1回の返済で元金および利息の全額を完済する事例でしたが、返済が複数回にわたる場合は、払いすぎた利息は元金の返済に充てられます。
例えば、100万円を1年毎に2回(元金均等)で返済する約束で、利率20%で借り入れた場合、最初の返済期日には20万円の利息が発生し、元金の50万円を加算した70万円を返済することになりますが、利息制限法の上限利率は15%となりますので、支払った20万円の利息のうち5万円は過払い金となります。
そして、この5万円の過払い金は、最高裁判決により残元金の返済に直ちに充てることが認められましたので、この事例では、1回目の返済が完了した段階で元金は45万円(50万-5万)になります。
そして2年後の2回目の返済では、約定利率を前提とすると50万円に1年分の利息10万円を加算した60万円を返済することになりますが、利息制限法の上限利率で計算すると、返済しなければならない元金は45万円で、利息は9万円となり、合計54万円となりますので、60万円から54万円を差し引いた6万円が過払い金になります。
仮にこの契約が100万円の限度額まで何度でも借り入れをすることができる継続的金銭消費貸借で、完済の翌日に再度100万円を借り入れた場合、6万円の過払い金は直ちに新たな借り入れの返済に充てられ、残元金は94万円になります。
この点について、厳密には、6万円の過払い金に対する利息も元金の返済に充てられますが、便宜上無視して説明しています。
4 残る問題
以上が過払い金の計算方法とその具体例となりますが、取引に空白期間がある場合に、前の取引で生じた過払い金を後の取引で借り入れた金額に充当できるかどうかについては、とくに前の取引と後の取引が別々の基本契約に基づく場合について、最高裁判決の基準の適用を巡って争いになることが多くなっています。
過払い金返還請求における弁護士法人心の強み
1 いずれなくなる事件類型

過払い金返還請求とは、利息制限法の上限利率を超える利率で貸し付けをしていた消費者金融やクレジットカード会社に対し、上限利率を超える部分の利息の返還を求める手続きです。
かつては、利息制限法の上限利率を超える利率で貸し付けをした場合でも、当時の貸金業規制法で定められていたみなし弁済の要件を充足すれば、利息制限法の上限を超える利息の収受も有効とされていました。
しかし、みなし弁済が成立する要件を厳格に解釈する最高裁判決が出され、ほとんどの利息の収受がみなし弁済の要件を満たさないこととなったため、2000年代半ばころから過払い金返還請求が隆盛となりました。
そして、2010年6月18日に施行された改正貸金業法により、みなし弁済は廃止されることとなったため、同日以降は利息制限法の上限利率を超える利率での貸し付けはできなくなり、実際、消費者金融やクレジットカード会社は、改正貸金業法が施行される数年前頃から、新規契約の貸付利率を利息制限法の上限利率以下に下げていました。
このように、過払い金返還請求は、みなし弁済が定められていたころに消費者金融やクレジットカード会社から利息制限法の上限利率を超える利率で借り入れを行っていた方が対象であり、そのような方の多くは既に過払い金返還請求を行っていますので、現在では、過払い金返還請求事件は大幅に減っています。
2 過払い金返還請求事件の経験数
過払い金返還請求で争いとなる点には変遷があり、過払い金返還請求が隆盛だったころにはほとんど争点となっていなかった部分が現在は重要な争点となっているということもあります。
しかし、過払い金返還請求事件の件数は大幅に減っていますので、過払い金返還請求事件をほとんど扱ったことがない、または全く扱ったことがない弁護士も増えていると思われます。
また、一般民事系の法律事務所の場合、過払い金返還請求が隆盛のころは相当数扱っていたとしても、現在はほとんど相談、依頼がないという事務所も増えていると思います。
現在の過払い金返還請求の実務について熟知していない弁護士だと、現在争点とされる点について、上手く対応できないことも想定されます。
この点、弁護士法人心では、設立当初から過払い金返還請求を主力業務の一つと位置付けて積極的に集客し、現在でも、事件数は減っているものの継続的に依頼を受けており、また、事務所内で定期的に情報交換も行っているため、現在の争点についても十分対応することが可能です。
過払い金返還請求をご検討の方は、ぜひ当法人までご相談ください。
過払い金の返還請求をするために必要な費用
1 過払い金返還請求の方法

過払金返還請求の手続きは以下のような流れになります。
① 対象業者から取引履歴を取り寄せる。
② 取り寄せた取引履歴を基に過払い金を計算する。
③ 業者に対し過払い金の返還を請求し、交渉する。
④ 交渉がまとまったら、合意書を作成する。
⑤ 合意で決めた期限までに業者から過払い金が振り込まれる。
交渉がまとまらない場合等は、訴訟を提起して解決することになります。
2 過払い金返還請求をするために必要な費用―弁護士報酬
過払い金返還請求を弁護士に委任して進める場合の費用には、大まかに分類して弁護士報酬と実費があります。
弁護士報酬には、着手金、成功報酬金、日当があります。
着手金は、弁護士が委任事件に着手する際に必要となる弁護士報酬で、成功報酬金は過払い金を回収した際に必要となる弁護士報酬です。
着手金については、弁護士法人心では、約定残債務がある場合は任意整理としての着手金をいただいておりますが、約定残債務がない場合(完済している場合)は着手金はいただいておりません。
成功報酬金は、弁護士法人心では、過払い金を実際に回収できたときに必要になります。
業者の倒産等により回収ができなかったときは発生しません。弁護士法人心では、成功報酬金の最低金額を2万円(税別)とし、原則として回収金額の18%相当額(税別)を成功報酬金としていただいております(ただし、回収のため強制執行を行う場合は別途費用が必要になります)。
日当は、訴訟を提起し、担当弁護士が裁判所に出廷した場合に必要になります。
訴訟を提起せずに解決した場合や、訴訟を提起しても第1回期日前に訴訟外で和解が成立し出廷しなかった場合は発生しません。
なお、成功報酬金および日当は相手業者から回収した過払い金からお支払いいただいております。
3 過払い金返還請求をするために必要な費用―実費
実費とは、弁護士が受任業務を遂行する上で必要になった郵便代、印紙代、コピー代、交通費等になります。
弁護士法人心では、実費については実際に必要になった金額のみいただいております。
なお、過払い金返還請求では、訴訟を提起しないで解決した場合、実費はそれほどかかりませんが、訴訟を提起した場合は、請求金額に応じた収入印紙と、訴状等の送達用の郵便切手を裁判所に納付する必要があり、収入印紙は、請求金額が大きいと数万円になることもあります。
ただ、これらの実費も回収した過払い金で十分賄えますので、ご心配は不要です。
過払い金の対象になる方、ならない方
1 過払い金返還請求の現状

大手の消費者金融であった武富士が、激増する過払い金返還請求に耐え切れず会社更生法の適用を申請したのは2010年9月でした。
当時は、東京地方裁判所には過払い金返還請求を主に扱う部も設置され、簡易裁判所の訴訟のほとんどが過払い金返還請求でした。
武富士の倒産から10年以上が経過し、過払い金返還請求の案件はだいぶ少なくなっています。
逆に、過払い金返還請求の相談では、その対象にならない方からのご相談申し込みも増えています。
本稿では、過払い金の対象になる方、ならない方についてご説明します。
2 いつから利用していても対象とならないケース
過払い金は、いわゆるグレーゾーン金利での貸付を行っていた業者からグレーゾーン金利で借り入れをしていた場合に発生します。
グレーゾーン金利での貸付が可能だったのは貸金業法が適用される消費者金融またはクレジットカード会社ですので、貸金業法が適用されない銀行や信用金庫から借り入れをしていた場合は、古くから借り入れていたとしても過払い金は一切発生しません。
また、グレーゾーン金利で借り入れをしていた場合に発生しますので、ショッピング(立替払い)では過払い金は発生しません。クレジットカード会社の場合、キャッシングまたはローンは過払い金が発生している可能性がありますが、ショッピングでは発生しないことになります。
3 グレーゾーン金利廃止後に新規に借り入れたケース
⑴ グレーゾーン金利は、2010年6月18日に完全施行された改正貸金業法により廃止されました。つまり、同日以降、消費者金融やクレジットカード会社はグレーゾーン金利での貸付ができなくなりました。
そのため、2010年6月18日以降に消費者金融会やクレジットカード会社と新規契約して借り入れを始めたという場合は、過払い金の対象には一切なりません。
⑵ また、ほとんどの業者は、2010年6月18日よりも前にグレーゾーン金利での新規貸付契約を止めています。
そのため、対象業者がグレーゾーン金利での新規貸付契約を止めた後に当該業者から新規に借り入れを開始した場合は、過払い金の対象にはなりません。
⑶ 消費者金融会社やクレジットカード会社の中には、グレーゾーン金利での貸付が可能であった時期でも利息制限法の上限利率以下での貸付しか行っていなかった業者もあります。例えば、SMBCがこれに該当します。
このような業者から借り入れをしていた場合は、古くからの借り入れでも過払い金の対象にはなりません。
4 まとめ
以上をまとめると、過払い金の対象となるには、
① グレーゾーン金利での貸付が可能であった業者から借り入れをしていたこと
② 2010年6月18日よりも前で、かつ対象業者がグレーゾーン金利での新規貸付契約を停止するよりも前に対象業者と契約して借り入れをしていたこと(なお、対象業者がグレーゾーン金利での新規貸付契約を停止する前にグレーゾーン金利での貸付契約を締結していた場合、停止後の借り入れもグレーゾーン金利での借り入れになっていることがありますので注意してください)
以上2点がまず必要になります。詳細は弁護士にご相談ください。
過払い金の消滅時効
1 過払い金が発生する取引

過払い金は、消費者金融やクレジットカード会社からグレーゾーン金利で借り入れていた場合に発生しますが、2010年6月に施行された改正貸金業法により、グレーゾーン金利での貸付はできなくなりました。
実際は、2007年頃までには多くの業者が新規契約者の貸付金利を利息制限法の上限以下に変更していましたので、過払い金が生じる取引を現在も継続しているというケースはそれほどないのではないかと思います。
つまり、過払い金が発生する取引の多くは既に完済等により終了しているのではないかということになりますので、以下にご説明する過払い金の消滅時効に注意する必要があります。
2 過払い金の消滅時効の起算点と時効期間
消滅時効の起算点とは、消滅時効の期間を計算するためのスタート地点です。
過払い金返還請求権の場合、そのスタート地点は、原則として最後の取引を行った時点になります。
約定利率に基づく残高(約定残債務)を完済した場合は、最後の取引は返済になりますが、約定残債務が残ったまま返済を止めてしまった場合は、最後の取引が貸付になることもあります。
過払い金は、この最終取引日から10年が経過することにより、時効で消滅することになります。
ただし、民法の消滅時効を改正する規定が2020年4月1日に施行されているため、同日以降に最後の取引を行った場合は、最後の取引日から10年が経過していなくても、過払い金返還請求権を行使できることを知った時から5年を経過すれば、時効により消滅しますので注意が必要です。
3 最終取引日より前に時効のカウントがスタートするケース
なお、最近では、最終取引日よりも前に時効のカウントがスタートすることを認める裁判例が出てきています。
具体的には、貸金業者が貸付停止措置(利用限度額を0円にすることです)を行い、その後は返済のみを継続しているケースについて、貸付停止措置が行われた時点(または利用者がその措置が行われたことを知った時点)から消滅時効のカウントがスタートすることを認めています。
例えば、2012年7月1日に貸付停止措置が行われ、2015年7月1日に完済した場合、最終取引日を時効の起算点とすると時効が完成するのは2025年7月1日ですが、貸付停止措置が行われた日を時効の起算点とすると、時効完成日は2022年7月1日になります。
これを認める裁判例は多いとは言えませんが、東京高裁でも認める判決が出ています。利用限度額が0円になり、返済のみを行っていたという方は、できるだけ早く弁護士に過払い金返還請求の依頼をするとよいでしょう。
過払い金について相談する際に必要となる資料
1 過払い金返還請求の流れ

過払い金返還請求をご依頼いただきますと、受任弁護士はまず対象業者に対し受任通知を発送して取引履歴の開示を求めます。
取引履歴には、借り入れや返済の年月日および金額などの情報が記載されており、この情報を専用の表計算ソフトに入力することで過払い金の金額を算出することになります。
過払い金の金額が判明したら、対象業者と交渉し、交渉がまとまらなければ訴訟をして過払い金を回収することになります。
以上の流れからもわかると思いますが、過払い金の相談、依頼の際は、借り入れを行っていた業者名がわかれば、基本的に資料は不要です。
2 資料があった方がよいケース1
ただし、資料があった方がよいケースもいくつか存在します。
まず、借り入れや返済の記録について、業者によっては古い記録を廃棄ないし削除している場合があります。
例えば、クレジットカード会社の三菱UFJニコスの場合、ある種類のキャッシングについては平成7年より前の記録を廃棄しているため、平成7年以降の取引履歴しか開示されません。
この場合、開示された取引履歴の情報のみで過払い金の金額を算定し請求することも多いですが、平成6年以前の借り入れおよび返済の情報を含めて計算した方が過払い金の金額は明らかに多くなります。
そこで、より多くの過払い金を回収するためには平成6年以前の取引内容について推定して計算する必要がありますが、三菱UFJニコスの場合、返済は銀行口座からの振り替えとなりますので、当時の通帳があれば、返済の金額および年月日は判明します。
3 資料があった方がよいケース2
例えば、消費者金融のA社と平成7年4月から平成14年6月まで、および平成15年3月から平成25年8月まで取引があったとします。
つまり、取引が二つあり、最初の取引の終了から2回目の取引の開始まで約8か月の空白期間があるケースです。
この場合、最初の取引と2回目の取引を一体のものとして過払い金の計算を行った方が、別々に計算して合計するよりも金額は大きくなります。
そして、取引を一体として計算できるかどうかの判断にあたり、最初の取引と2回目の取引の金銭消費貸借基本契約が同じか違うかが一つの重要なポイントとなります。
お手元に金銭消費貸借基本契約の契約書があれば同一基本契約による取引かどうかがわかりますが、返済等を行った際に受け取ったATM明細にも基本契約日が記載されていることがありますので、2回目の取引の際のATM明細があれば、最初の取引の基本契約と同じかどうかが判明することになります。
業者によっては、基本契約は同一なのに違うと主張するケースもあります。
同一基本契約をベースに契約の一部を変更する契約をすることがあり、業者は、この変更契約を新たな基本契約であると主張します。
2回目の取引で受け取ったATM明細に最初の取引の契約日が基本契約日として記載されていれば、業者に対し有効な反論をすることができます。
この2つのケース以外にも資料があった方がよいケースはありますので、依頼した弁護士の指示にしたがって準備してください。