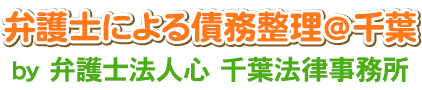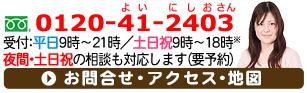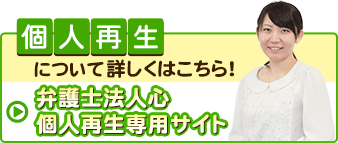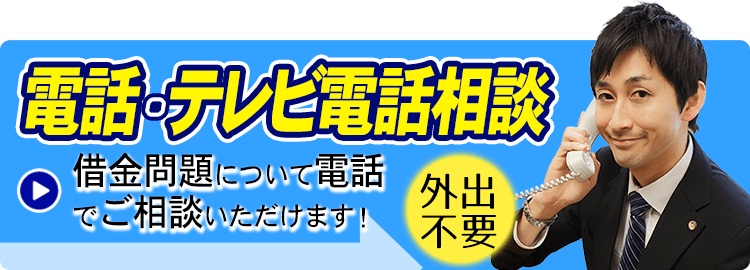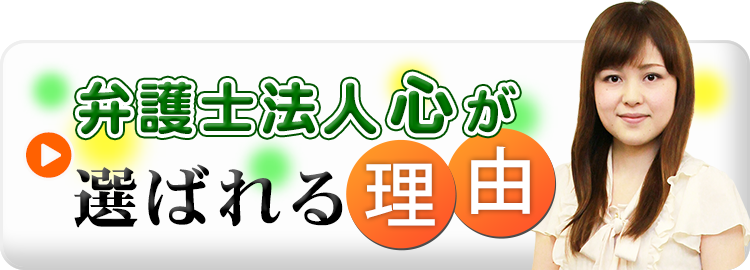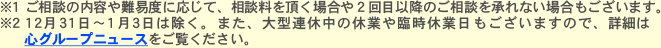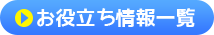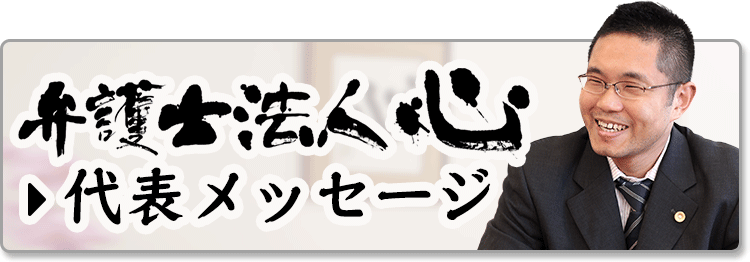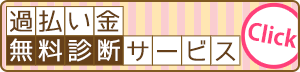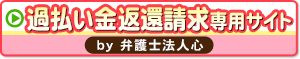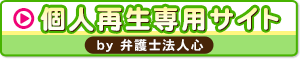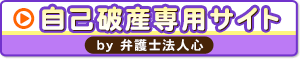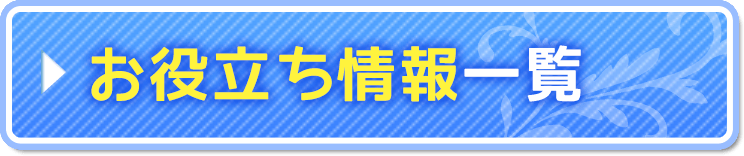個人再生のご相談をお考えの方へ
借金の総額が減ることによって返済が可能になるような場合には、個人再生という手続きをご検討ください。
個人再生を行うことにより、負債を圧縮して長期間で返済できるようになる可能性があります。
個人再生が認められるかどうか、それによりどの程度金額を圧縮することができるかということは、個々の状況によって異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。
当法人には個人再生を得意としている弁護士が在籍しており、しっかりと見通しなどをご説明するとともに、手続きがスムーズに進むよう対応させていただきます。
千葉にお住まいで、個人再生に関して疑問などがある場合にも、お気軽にご質問ください。
駅近くでのご相談が可能
当法人の事務所は駅の近くにありますので、ご相談にお越しいただく際にも便利です。千葉駅の近くにも事務所があります。所在地などの詳細はこちらをご覧ください。
個人再生をした場合の債務額
1 減額された債務を返済する手続き

個人再生は、個人(自然人)の方を対象とした債務整理の手段の一つで、地方裁判所が管轄し、一定のルールに従って減額された債務を原則3年で返済することになります。
ここでは、一定のルールに則って減額された債務、つまり個人再生手続で最低限弁済しなければならない金額(これを最低弁済額と言います)についてご説明します。
なお、この一定のルールは複数ありますが、それぞれのルールで決まる金額のうち最も多い金額が最低弁済額になります。
2 再生債権額を基準として決まる金額
確定した再生債権額(以下「債権額」と略して表記します)を基準として決めるルールは以下のとおりとなります。
①債権額が100万円未満の場合
→債権額全額
②債権額が100万円以上500万円未満の場合
→100万円
③債権額が500万円以上1500万円未満の場合
→債権額の5分の1の金額
④債権額が1500万円以上3000万円以下の場合
→300万円
⑤債権額が3000万円を超えて5000万円以下の場合
→債権額の10分の1の金額
例えば、債権額が1250万円の場合、最低弁済額はその5分の1である250万円になります。
3 清算価値を基準として決まる金額
清算価値とは、再生債務者が所有する財産の総額のことを指します(清算価値の計上方法については細かいルールがありますが、ここでは省略しますので別稿をご覧ください)。
破産手続では、破産者が所有する財産は原則として換価処分され、破産債権者への配当に充てられますので、個人再生手続きにおいても、再生債務者はその有する財産以上の金額を返済しなければならないというルールがあり、これを清算価値保障原則といいます。
例えば、再生債務者が現金5万円、預貯金80万円、解約返戻金見込額が70万円の保険、時価35万円の自動車を有する場合、千葉地方裁判所の基準では、清算価値保障原則により決まる最低弁済額は185万円となります。
この例で、仮に再生債権額が500万円の場合、再生債権額を基準に決まる最低弁済額は100万円になりますが、清算価値を基準にすると185万円となりますので、小規模個人再生では185万円が最低弁済額となります(給与所得者等再生では後述のとおりもう一つ基準があります)。
4 可処分所得を基準として決めるルール
個人再生手続きにおける可処分所得とは、再生債務者の収入から、所得税、住民税および社会保険料を控除し、さらに、政令で規定された生活費の金額を控除した後の所得をいいます。
給与所得者等再生では、この可処分所得の2年分以上を返済しなければならないというルールが加わることになります。
例えば、可処分所得が150万円であれば、このルールで決まる最低弁済額は300万円となり、上記3の事例(再生債権額が500万円で清算価値が185万円のケース)で給与所得者等再生を選択すると、最低弁済額は300万円になります。
この可処分所得は、扶養家族の人数等にもよりますが、一般的に高額になる傾向があります。
個人再生の手続きの期間
1 受任から申し立てまで

借金等の返済が厳しくなり、債務整理は回避できないとなった場合、弁護士に相談し、債務整理ができるかどうか、できるとしてどの手続きを選択するかを検討することになります。
検討の結果、個人再生を選択することに決めたら、費用について弁護士と協議し、その支払い方法を決めることになります。
そして、個人再生の申立ては、原則として費用の準備が完了してから行うことになりますので、個人再生の手続きの期間は、この費用の準備期間の影響を大きく受けることになります。
例えば、解約返戻金のある保険があり、その保険の解約により費用を一括で準備できる場合は、通常、受任後2~3か月程度で申立てが可能ですが、費用を10回の分割で積み立てる場合は、申立てまで10カ月程度かかることになります。
なお、費用を分割で積み立てる場合は積み立てと並行して申立ての準備を進めることになりますが、費用を一括で準備できる場合でも、申立ての準備のための標準期間として2~3か月程度は想定しておいた方がよいでしょう。
2 申し立て後、開始決定まで
千葉地方裁判所およびその支部では、個人再生の申立てを行うと、通常、裁判所から補正の指示があります。
具体的には、不足資料の提出や、申立書等の不明点について説明を求められることになります。
補正の指示への対応が完了すると、再生手続きの開始決定が出されることになります。
なお、千葉地方裁判所およびその支部では、弁護士が代理人として申立てを行う場合、原則として個人再生委員は選任されませんが、選任された場合は、補正の対応後に個人再生委員の面接を受けることになります。
申立て後から開始決定までの期間については、補正指示への対応に必要な期間や個人再生委員選任の有無にもよりますが、千葉地方裁判所の本庁では、3週間から1か月を想定しておくとよいでしょう。
ただ、一部の支部では、補正の指示がなされるまでに1か月程度かかることもあり、そうなると、申立てを行ってから開始決定まで優に1か月以上かかることになります。
3 開始決定後、再生計画の認可決定確定まで
裁判所での再生手続きは、再生計画の認可決定が出され、それが確定することで完了となります。確定後、再生計画にしたがった返済が開始します。
再生計画の認可決定が出され、それが確定するまでの期間は千葉県内のどの裁判所でも1か月前後です。
他方、開始決定から再生計画の認可決定が出されるまでの期間ですが、再生債権について異議の申述がなされない通常の案件を前提とし、異議申述期間の終期から1週間程度で再生計画案を提出した場合は、千葉地方裁判所の本庁では3か月程度となります。
以上をまとめると、千葉地方裁判所の本庁で、再生債権に対する異議が提出されない通常の事案では、申立てから再生計画認可決定の確定まで5か月程度ということになります。
個人再生で必要な費用
1 個人再生をお考えの方へ
個人再生を検討している方が最も気にしている事項の一つは、個人再生を行った場合に必要となる費用だと思います。
本稿では、弁護士に依頼し千葉地方裁判所またはその支部で個人再生手続きを行うことを前提に、個人再生をするのに必要な費用についてご説明します。
2 裁判所で必要になる費用

まず、裁判所で必要になる費用についてご説明します(本稿執筆時の金額です)。
⑴ 収入印紙
1万円分の収入印紙を申立書に貼付します。なお自己破産の場合は1500円です。
⑵ 予納郵券
個人再生手続きでは(自己破産も同様です)電子納付が認められていないため、裁判所が指定する郵便切手を予納する必要があります。
合計金額は4280円となりますが、給料差押えを受けている場合等、強制執行等の中止命令の申立てを同時に行う場合はさらに2178円分の予納が必要です。
⑶ 予納金(官報公告費)
官報公告費として予納する金額は1万3744円になります。官報には、再生手続きの開始等が公告されることになります。
⑷ 再生委員費用
千葉地方裁判所およびその支部の場合、弁護士が代理人として個人再生の申立てを行った場合は原則として個人再生は選任されませんが、法律上の
問題がある場合や、履行可能性に問題がある場合等は選任されることがあります。
選任された場合、住宅資金特別条項を定める場合は20万円、定めない場合は15万円の費用が必要になります。
この費用は原則として一括で予納する必要がありますが、一部を予納して残りを分割で支払う(履行テストを兼ねることになります)ことも可能です。
3 依頼する弁護士にかかる費用
依頼する弁護士に支払う費用は、弁護士報酬と実費に大きくわけることができます。
まず実費は、弁護士が当該依頼者の委任事務を処理する上でかかる費用になり、具体的には郵便代、コピー代、交通費等になります。
実費については、定額を請求する法律事務所と実際にかかった費用のみ請求する法律事務所がありますが、弁護士法人心では原則として実費については実際にかかった費用のみ申し受けております。
なお、本稿の執筆者が担当する通常の個人再生手続きでは、委任事務の処理に必要な実費は1万円から2万円程度です。
次に弁護士報酬ですが、弁護士法人心では、個人再生手続きで弁護士報酬として申し受けるのは着手金および日当・出張費で、過払金回収等がない限り成功報酬は不要です。
着手金の金額については、定額にする法律事務所もありますが、弁護士法人心では最低金額を定め、事案の内容に応じて増額する方式を採用しています。
個人再生をする場合の流れ
1 個人再生手続きについて

個人再生は、裁判所で行う債務整理の手続きで、法律の規定等に従い減額された負債を原則3年間、最長5年間で返済すれば、残りが免除されるという手続きです。
本稿では、千葉地方裁判所を前提として、個人再生をする場合の流れについて、一般的なケースを念頭にご説明します。
なお、千葉地方裁判所には千葉中央にある本庁の他にも複数の支部があり、支部によっては本庁と手続きの流れが少々異なる場合もあります。
ここでの説明は、本庁の手続きを前提としています。
2 依頼から申立てまで
⑴ 費用の準備
個人再生をご依頼いただくと、まず手続きを進めるにあたって必要となる費用(着手金や実費等)を準備していただきます。
預貯金や賞与、または保険の解約返戻金などですぐに費用を準備できる場合、即座に申立ての準備に進むことになります。
費用の全部または一部を分割で準備いただく場合には、費用の準備期間を設けることになります。
また、依頼の際に、クレジットカード払いになっている料金の支払い方法の変更や、不要と思われる保険の解約、車や不動産の査定書の取得、家計簿の作成など、担当弁護士から指示のあった事項については速やかに対応していただくことになります。
⑵ 住宅ローン特則を利用する場合の留意点
債権者に対する返済は、依頼後はストップすることになりますが、住宅ローン特則を利用する場合は、住宅ローンの返済は継続します。
⑶ 裁判所への申立て
費用準備の目途が立ちましたら、申立ての準備に入ります。
住民票、預貯金の通帳や明細、収入資料、財産の資料、家計表など、申立てにあたり必要な資料等を準備いただきます。
資料等の準備ができましたら、担当弁護士が申立書を仕上げ、管轄の地方裁判所に申立てを行います。
3 申し立て後
⑴ 裁判所への対応
個人再生の申立てを行うと、通常、申立ての内容などについて裁判所から問合せがあります。
この問合せについては回答期限が設けられますので、速やかに対応する必要があります。
また、住宅ローン特則適用の可否など法律的な問題がある場合や、履行可能性に疑義がある場合は、個人再生委員が選任されることになります。
個人再生委員が選任された場合は、その費用の準備について協議することになります。
⑵ 個人再生手続きの開始
裁判所からの問合せにすべて対応し、また個人再生委員が選任された場合は再生委員との面接を終えると、裁判所の決定により個人再生手続きが開始することになります。
個人再生手続きの開始後は、依頼者の方に主体的に行っていただくことは履行テストの入金のみとなるのが通常です。
債権届出書についての対応や再生計画案の作成は、受任した弁護士が行うことになります。
⑶ 再生計画の認可決定
受任弁護士が再生計画案を提出し、その内容について問題がなく、かつ履行テストも滞りなく行われていれば、裁判所は、再生計画を認可することになります。
なお、小規模個人再生で半数以上の再生債権者が再生計画案に反対した場合等は認可されません。
再生手続きの開始から再生計画の認可決定まで、通常は4か月程度となります。
4 再生計画認可決定後
再生計画について認可決定を行うと、裁判所は、その内容を官報で公告します。
そして、官報に掲載されてから2週間が経過すると、認可決定が確定することになります。
認可決定が確定した後は、再生計画の内容にしたがい各再生債権者に分割弁済をすることになります。
以上が個人再生手続きの大まかな流れになります。
個人再生の手続きをとるメリット・デメリット
1 個人再生とは

個人再生は、裁判所を利用して行う債務整理の手続きです。
法律が定める基準に従い減額された負債を、原則3年間、最長5年間で完済すれば、残額が免除されることになります。
返しきれないほどの多くの負債を抱えた方にとっては、経済的に立ち直るために有益な手続きかと思います。
ここでは、個人再生のメリット・デメリットについて、他の債務整理の手続きと比較してご説明します。
2 任意整理と比較した場合のメリット・デメリット
⑴ 任意整理と比較した場合の個人再生のメリット
第一のメリットとしては、負債の減額を受けられることです。
例えば、負債総額が500万円の場合、小規模個人再生では、再生債務者の方に100万円を超える財産がなければ、100万円を分割返済すれば、残りの400万円は免除されることになります。
任意整理の場合は、分割返済の場合に元金の減額を受けられることはほとんどありません。
また、小規模個人再生の場合、返済の金額や返済期間の案を記載した再生計画案について再生債権者の一定数の不同意がなければ原則として認可されますので、任意整理に応じない業者がある場合でも、個人再生であれば強制的に分割返済に従わせることができるというメリットもあります。
⑵ 任意整理と比較した場合の個人再生のデメリット
個人再生ではすべての負債が対象となりますので、例えば自動車ローンが残っている場合、個人再生を行うと、所有権がローン会社に留保されている自動車は引き揚げられてしまうという点にあります。
また、個人再生は裁判所で行われる手続きで、家計表等の書類を作成しなければなりませんし、個人再生を行った場合の返済の可能性も厳密に吟味されます。
比較的手軽にできる任意整理に比べると、依頼者の方のご負担が重くなるというデメリットもあります。
3 自己破産と比較した場合のメリット・デメリット
⑴ 自己破産と比較した場合の個人再生のメリット
まずメリットのひとつとして、住宅ローンの残っている自宅を残しながらその他の債務(消費者金融からの借り入れやクレジットカードの利用残額など)を整理できることです。
住宅資金特別条項を使うことで、この目的を達成することができます。
破産手続では、住宅ローンの残っている自宅は手放さなければならないことになるため、自宅を手放したくないという方にとってはメリットがあると言えます。
また、自己破産では一定の職業や資格についてその制限が定められていますが、個人再生では制限はありません。
この点も個人再生のメリットです。
さらに、自己破産と異なり免責不許可事由というものが定められていませんので、免責不許可事由がある場合でも比較的安心して利用することができます。
⑵ 自己破産と比較した場合の個人再生のデメリット
他方、個人再生は返済を前提とした手続きとなりますので、安定した収入がない場合は、利用の難易度は上がります。
また、減額されるとはいえ一定金額の負債を分割返済しなければならないため、免責決定により負債全部が免除される自己破産と比較すると、経済生活の立て直しは遅れる可能性があります。
これらは、自己破産と比較した場合のデメリットと言えます。
個人再生をすることができる条件
1 個人再生とは
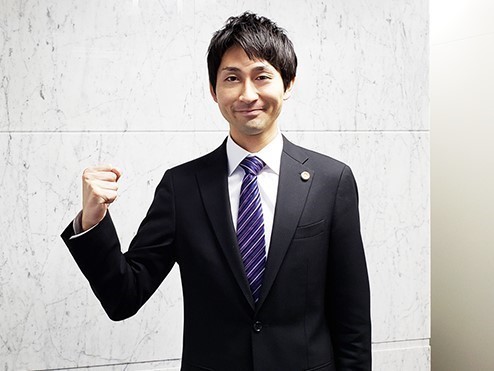
個人再生とは、裁判所で行う債務整理の手続きで、法律の規定にしたがって減額された負債を原則3年、最長5年で分割返済すれば、残りは免除されることになります。
個人再生手続きについては、民事再生法という法律が規定しており、利用するための要件についてもこの法律に規定されています。
ここでは、個人再生を行うにあたって重要な要件の一つである収入についてご説明します。
2 収入について
個人再生手続きでは、法律にしたがって減額された負債を原則3年、最長5年で分割返済することになります。
そのため、その減額された負債を分割で返済できる収入があるかどうか、あるとしても、返済期間中継続してその収入を得ることができるかどうかが問題となります。
例えば、700万円の負債があり、個人再生手続きで140万円を返済しなければならないとすると、3年間の分割だと月々約3万9000円、5年間の分割だと月々約2万4000円の返済となります。
月々の手取りが20万円で、家賃等の生活費で月々18万円程度かかっている場合は、返済にあてる金額が不足しており、個人再生手続きを利用するのは難しいという判断になります。
また、返済期間中に継続して収入を得ることができるかという観点からも見てみましょう。
上記の例と同様に700万円の負債があり個人再生手続きで140万円を返済しなければならないケースで、月々の手取りは30万円あるものの、現在の年齢が64歳であり、勤務先の定年が65歳の場合、定年後に返済が十分可能な収入が見込めないとなると、個人再生の利用は難しくなります。
3 職業の種類
個人再生を行う方は会社で正社員として働いている方が多いですが、正社員でなくても個人再生を利用することは可能です。
ポイントは、個人再生で返済しなければならない金額を現在の収入から捻出することが十分可能かどうかという点と、その収入が継続して得られるかどうかという点になります。
そのため、契約社員として働いている方でも、同じ会社に長期間勤務している場合は、その後も3年から5年程度は継続して勤務できる見込みと判断されれば、そのようなケースでも個人再生を利用することが可能です。
また、アルバイトでも、人手不足が顕著で失職する可能性が低い業種に長年勤めているようなケースでは、個人再生を利用することが可能でしょう。
収入の面で個人再生を利用できるかどうかについては、ケースバイケースの判断となりますので、詳細は弁護士にご相談ください。