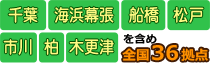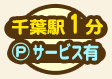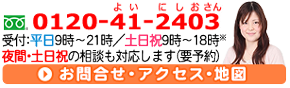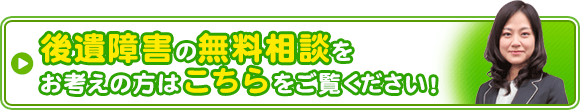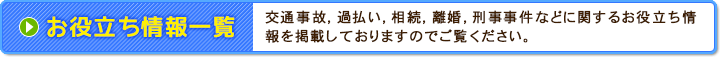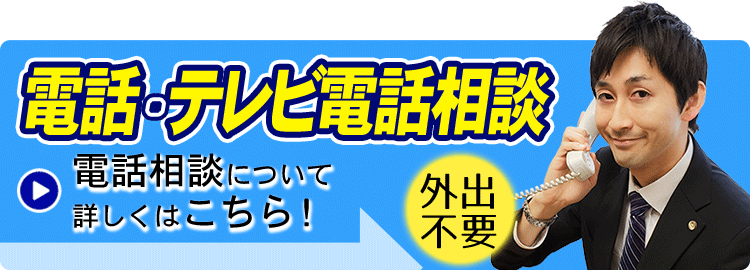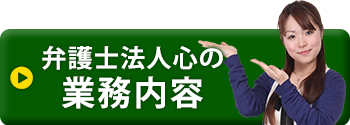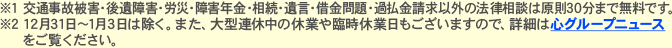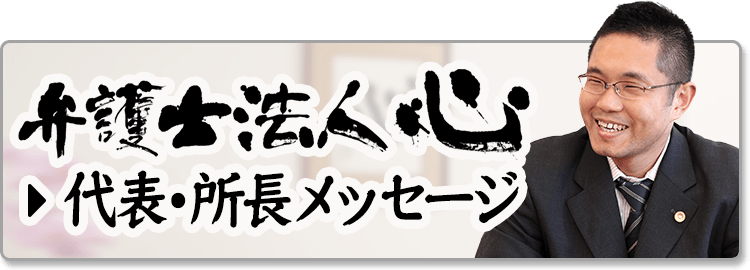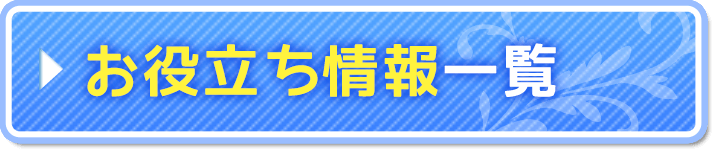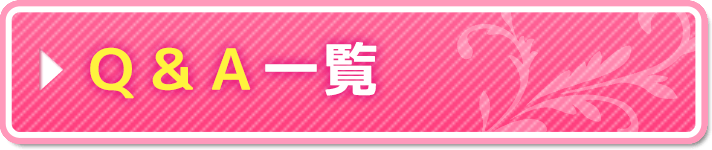脊髄損傷になった場合の後遺障害の認定に関するQ&A
脊髄損傷ではどんな症状が生じますか?
脊髄損傷は、脊髄が交通事故外傷などによって損傷を受け、神経の伝達が阻害されることで運動機能、感覚機能、排泄機能などに障害が生じる疾患です。
脊髄損傷の後遺障害等級にはどのようなものがありますか?
1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級があります。
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するものは1級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するものは2級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないものは3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないものは5級2号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないものは7級4号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるものは9級10号
局部に頑固な神経症状を残すものは12級13号
に該当します。
脊髄損傷で後遺障害が認定されるために重要なものには何がありますか?
MRI、CT等の画像所見はもちろんですが、神経学的所見の有無やその内容、脊髄症状判定用の内容などがとても大切です。
脊髄損傷は、画像所見上明らかでない限り、原則として後遺障害として認定されず、画像所見上明らかである場合に、神経学的所見の内容や脊髄症状判定用の内容などを考慮して、等級を決定することになります。
脊髄症状判定用は、日常生活や社会生活上の支障を記載する箇所が含まれており、かつ、医師が作成する書類であるため、医師が被害者の症状や日常生活及び社会生活上の支障を正確に把握していない場合には、実際の症状や支障よりも軽い症状や支障が記載されてしまい、低い等級しか認定されないことがあります。
そのため、医師に脊髄症状判定用を作成していただく場合には、事前に、実際の症状や支障を正確に伝えたうえで、作成を依頼することが大切です。
非器質性精神障害の後遺障害申請にはどのような特徴がありますか? 高次脳機能障害となり働けなくなった場合のQ&A