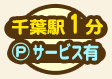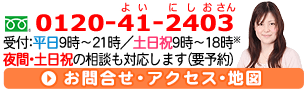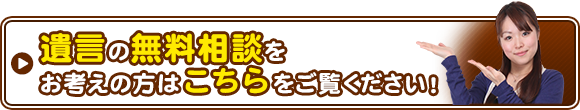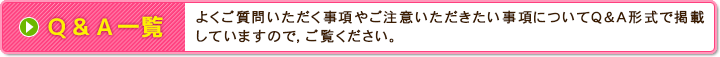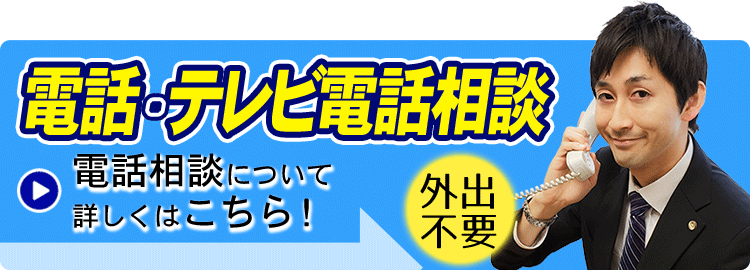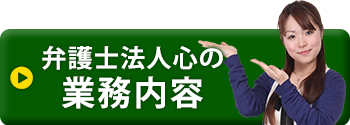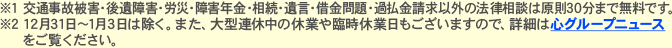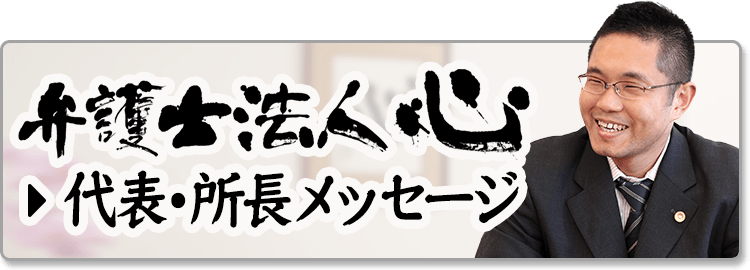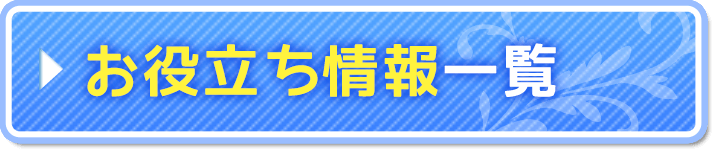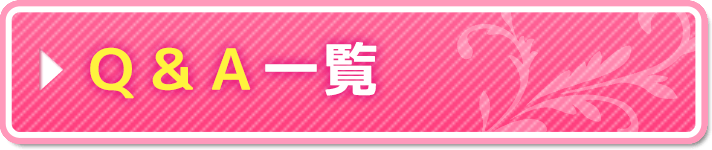遺言の種類とその特徴
1 遺言には種類があります
ご自身が亡くなった後の財産の取扱いについて、遺言を作成してご自分の意思を反映させたいとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
遺言にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴がありますので、実際に遺言を作成される際には、ご自分の目的に合った種類のものを選ぶことが大切です。
ここでは、遺言の中でも、実際に使われる機会が多い公正証書遺言と自筆証書遺言について説明します。
2 公正証書遺言
遺言の中で、無効になりにくいという点でおすすめできるのが、公正証書遺言です。
公正証書遺言は、公証役場に行き、公証人と遺言者および証人2名の立会いの下で作成します。
公証役場に行くことが難しい場合は、公証人に出張してもらい、別の場所で作成することも可能です。
公正証書遺言は、遺言者の意思や判断能力について、公証人が確認をしているため、無効になりにくいという特徴があります。
また、遺言を執行する際の検認が不要であることも、特徴のひとつです。
しかし、遺産をどのように分けるのがよいのかなど、遺言書の内容について公証人がアドバイスしてくれることはありません。
そのため、ご自分にとって望ましい内容の遺言書を作成するためには、専門家に相談することが必要となります。
公正証書遺言の原本は、公証役場で半永久的に保管がされます。
そのため、万が一正本や謄本を紛失しても公証役場で再発行することができる、大変便利な制度です。
3 自筆証書遺言
⑴ 自筆証書遺言の特徴
全文自筆で記載をし、日付の記入、署名、捺印をすることで成立するのが、自筆証書遺言です。
遺言書の書き方に関する疑問をまとめておりますので、ご参照ください。
自筆証書遺言の特徴は、自分でも手軽に作れることですが、全文自筆で書く必要があるため、内容を作り込む場合には相応の労力を要します。
また、筆跡や認知能力等について、後から争われるケースがままあります。
自筆証書遺言を作成する場合には、その弱点を補完するため、作成する様子を動画で撮影しておく等の工夫が必要になります。
「全文自筆」というルールに関して、近年の法改正によって、相続財産目録についてはPC等でプリントアウトして、各ページに署名する方法でも足りることになりました(参考リンク:法務省・自筆証書遺言に関するルールが変わります。 )。
また、法務局による自筆証書遺言の保管制度ができたことにより、法務局保管の場合には従前は必要であった検認が不要となったほか、紛失のリスクも軽減できることになりました(参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度)。
この制度によって、自筆証書遺言の利便性も向上したと思います。
⑵ 自筆証書遺言を作成する際は弁護士への相談がおすすめ
自筆証書遺言を作成する際に弁護士が関与していないと、問題が生じるおそれがあります。
例えば、形式的に有効な遺言書を作成できておらず、せっかく作成した遺言が無効となってしまうケースが考えられます。
自筆証書遺言を作成した後で、訂正したり書き直しをしたりする場合にも、厳格なルールがありますので注意が必要です。
遺言の訂正や書き直しをする場合の方法については、こちらをご参照ください。
また、内容に問題がある遺言を作ってしまったために争いの火種になってしまったり、遺産の一部だけに関する遺言書を残したため残りの財産について揉めてしまったりと、トラブルの原因になってしまうケースもあります。
遺言によるトラブルを予防するためにも、作成する際は弁護士へご相談ください。
遺言についてお悩みの方へ 子どもがいない夫婦に遺言が必要な理由