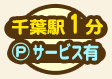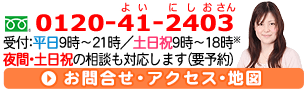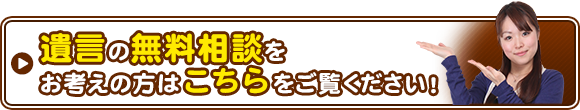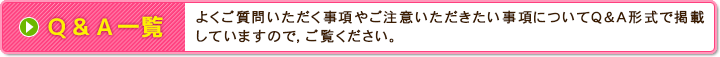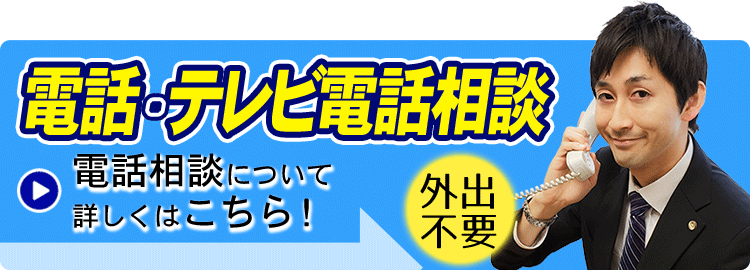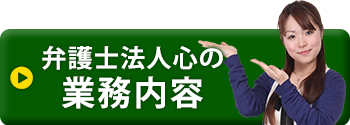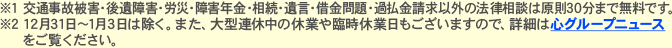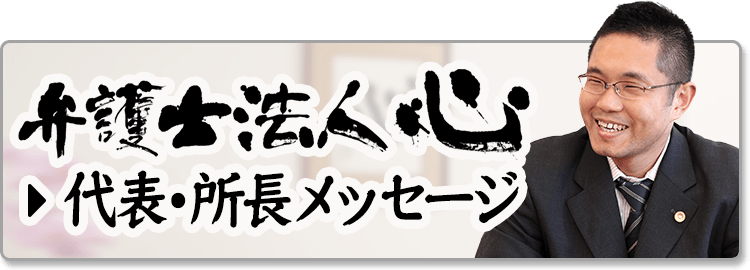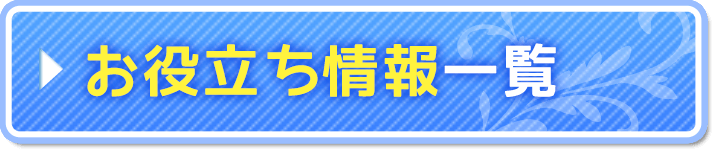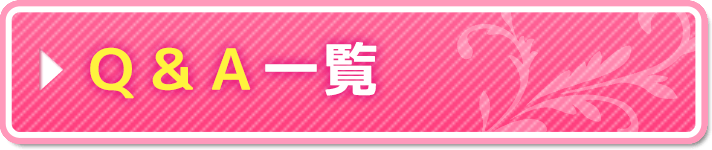遺言の訂正や書き直しをする場合の方法
1 自筆証書遺言の訂正や書き直しは厳格なルールに従う必要があります
遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があり、このうち実務上多く用いられるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は遺言者の方が原則としてすべて自筆で作成する遺言であり、法律によって厳格に書き方が定められています。
そして、法律によって定められた書き方を満たしていない場合、基本的には無効になってしまいます。
自筆証書遺言の訂正や、書き直しについても同様に、法律によって方法が決められています。
なお、公正証書遺言は原本が公証役場に保存されているため、遺言者が訂正や書き直しはできず、内容を変更したい場合には改めて公証役場で作成し直す必要があります。
以下、自筆証書遺言の訂正や書き直しの方法について、詳しく説明します。
2 自筆証書遺言の訂正や書き直しの方法について
自筆証書遺言の訂正や書き直しの方法は、民法第968条第3項に定められています。
【参考条文】(民法)
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
自筆証書遺言の訂正や書き直しをする際は、まず訂正したい部分に横線を引くなどして指示をします。
次に、指示した部分を変更した旨(どの部分を、どう書き換えたか)を付記します。
そして、付記部分に遺言者の方の署名をするとともに、変更した部分には元々遺言に用いている印鑑を押します。
これで自筆証書遺言の訂正や書き直しは完了します。
子どもがいない夫婦に遺言が必要な理由 遺産分割のことでお悩みの方へ